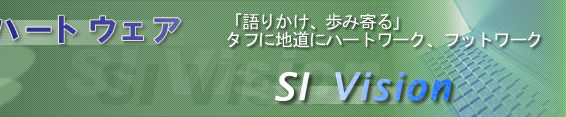ご縁があり富山を訪問するようになって、足掛け六年の月日が経過しました。最初のうちは二月に一度くらいの割合だったのに、それが今は毎月、呉羽丘陵麓の梨畑を見ながらハートウェアのオフイスに通っています。
富山といえば、春夏秋冬の立山連峰の絶景(いつも見える訳ではありませんが)のことだけでなく、美味しい水や米や魚のことについても、お蔭様で今は話せるようになりました。そして、車で街を行き来する度に「いいなぁ」と思うことは、道路にゴミの少ないことです。五年前に来たときには走る車の中から掃除をした直後の道路かと思うくらいにゴミの少ないのに驚きました(残念なことに、最近は少しゴミが多くなってきているように思います)。
先日、谷川社長ご夫妻、ガイドして下さる杉山様(杉山様には以前も二上山や雨晴海岸と万葉歴史館を案内していただきました)と一緒に高岡の街を歩きました。他のスケジュールが重なっていて高岡に着いた時間も遅く、強行軍での案内で、ハラハラさせたかと思いますが、瑞龍寺、高岡大仏、山町筋から金屋町と回りました。金屋町に着いたころには夕暮れが迫っていました。
静かな佇まいの金屋町、しかも夕暮れ迫るひととき、祭日なら人、人、人の中を行くのではないかと思うと、贅沢なタウン・ウオッチングが出来ました。古い日本の商家がそのまま残っているような千本格子(「さまのこ」というそうですね)の屋並、その一軒の大寺幸八郎商店に入りお土産を買いました。杉山様の説明で加賀藩二代藩主前田利長が他の地から鋳物師七名を招いて産業振興(ものづくりの基礎)を実現したことを知りました。
実はその前日に、ホテルの北日本新聞で「ものづくり立県への指針」を説いた石井知事を交えた地元産業人の座談会の記事を読んでいました。富山の文化は「消費の文化」というよりは「生産の文化」であること、観光が「その地域の光を観る」ことなら「富山のものづくり」は、まさに観光資源であり、「産業観光」が、富山まちづくりの基盤となり得るというYKK吉田社長様のご発言が、前田利長と重なりました。
釈迦に説法かと思いますが、 造られた商品や製品は人様に使われて初めてその価 値を発揮します。関西弁で言えば「役に立ってなんぼのものや」ということです。
ものづくりは優れた技術に支えられた「良い商品や製品」を生産することですが、優れた技術を支えるのは「つくる人の心」にあると思います。愛用される商品、便利な製品には、つくる人の心が乗り移っていなければなりません。ちょうど一年前のエッセーで書いた宮本武蔵の「五輪書」の「大工棟梁の心得」を思い出しました。(A)
* [註] エッセー・バックナンバー 第27回 「新日本様式協議会」
|