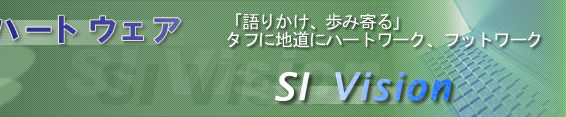良寛が、備中玉島の円通寺の師、国仙和尚から「良や愚の如く道うたた寛し。騰々任運誰か看ることを得む、為に附す山形爛藤の杖、到る処壁間午睡の閑。」(意訳「良寛よ、お前が修行して得た道は、周りからは理解されず愚かだと見られているかも知れぬが、お前の掴んだ道はなかなかの寛い道だ。お前はこの杖をもって好きなところに出かけて行けばよい。自然に任せ悠然としているそのままの姿で、お前の好きなようにすればよい。この杖を大事にしろよ。」)と、詩偈とともに一本の杖を授けられたことは前回に書いた。良寛は出雲崎尼瀬の光照寺で四年、円通寺で十二年の修行を続けてきたが、心底には逃れられない悩みを抱えたままに、以後の数年も過ごしていたように思われる。その辺りのところを今回は触れてみたい。
詩偈を与えて間もない寛政三年(1791年)三月に国仙和尚は入寂された。良寛は円通寺を出て師の教えに従うように四国、九州、近畿を数年にわたって遍歴している。その期間はおよそ四年になると大方の良寛研究家は推論しているが、この時期の良寛の行状を物語る資料は少なく、唯一、江戸の国学者、近藤万丈が若いときに四国の土佐を旅して大雨にあい、雨宿りを請うた粗末な庵に乞食のような僧がいて、その僧との不思議な出会いを著した「寝覚の友」という書が残っている。「その僧こそが、円通寺を出て修行遍歴を重ねていた良寛ではないか」と後に語られるところとなった。その近藤万丈の「寝覚の友」を忠実に採り上げた水上勉の良寛本から意を汲み取ると次のようなことになる。
七十歳、江戸小日向新屋敷にある椿園の主人になっていた近藤万丈が、二十年も前に書いた「寝覚の友」を、小日向に近い江戸川の曹洞宗田中寺の老僧が読み、実は越後生まれのこの老僧に頼まれ、断りきれなくて再び写したと自身で断り書きをした「寝覚の友」がある。これを現代風に書けばこうなる。『雨宿りを許された若き万丈が炉の側に座ると、いろ青く面やせた僧もまた炉の側に座ったままであった。この破れ庵には風を防ぐ襖もないようなもので、食べるものもない。とにかく雨さえしのげればと、炉のそばに上がらせてもらった。僧は最初にものを言っただけで、後は一言もしゃべらず、万丈が話しかけても只々微笑むだけであった。狂人ではないのかと不安もあったが、その夜は僧と共に炉の側で寝た。翌日になっても雨は反って激しく降り、「小雨になるまで今しばらくおいて欲しい」と願うと、「いつまででもどうぞ」と言ってくれ、昨夜泊めてもらったより嬉しかった。そして、麦の粉を湯にかき混ぜて食べさせてくれた。部屋には小さな
机があって、その上に二冊の本があり、何が書いてあるのかを開いてみれば、荘子の書であり、中にこの僧の作と思われる漢詩が草書で書かれ挟んであった。よく読めなかったが、草書のあまりの素晴らしさに感じ入り、手持ちの扇に賛を願うと、すぐさま筆をとって梅に鶯の絵などを描いてくれた。その賛には何を書かれたかはもう忘れたけれど、賛の末尾に「越州の産了寛書す」と、書いていたのだけは覚えている。』というものである。
その日も終日雨となり、近藤万丈は結局二夜をこの庵で過ごして、『次の日は朝から陽光が輝いた。例の麦の粉を食べ、出発するにあたって些かのお礼をしたいとお金を渡そうとしたが、僧は受け取らず、代わりに紙と短冊を渡したらこれは喜んで受け取った。その後、橘何某の著した「北越奇談」を読むと、小さいときから読書好きで、上手な字を書き、裕福な家に生まれながら世を遁れたという、あの僧こそが良寛であったかと、昔を思い出して、一夜感慨にふけった。』と締めくくっている。そして、上述のとおり『田中庵の大徳がこれを読んで、自分も越州の産であり良寛は懐かしい、是非とも書いてくれとの頼みなので、断りきれず再び写した。』ということなのである。
円通寺時代の良寛に話を戻す。ここで修行に励むうちにも良寛の悩みは尽きず、悩みから解放されなかった。「僧伽(そうぎゃ)」(僧の集団)という長い漢詩から、次の二つを読んでみることにする。
『我れ彼の朝野を適(ゆ)くに
士女おのおの作(しわざ)あり
織らずんば何を以て衣(き)
耕さずんば何を以て哺(はぐ)くまん
いま釈氏の子と称するは
行もなく亦悟もなし
徒(いたずら)に檀越の施(ほどこし)を費(ついや)して
三業相顧みず
頭を聚(あつ)めて大語を打(たた)き
因循旦暮を度(わた)る
外面は殊勝を逞しうして
他(か)の田野の嫗(おうな)を迷わす』
『我れ行脚の僧を見るに
都(すべ)て是れ可怜生(かれいさん)
三刹の地を履(ふ)まずば
衲僧の名を汚すと謂(おも)えり
所以(ゆえ)に本師を辞して
茫々策を杖いて行く
一夏此の地に住し
三冬彼の郷に到る
徒らに師の口頭を采(と)り
之を以て平成に充(あ)つ
相逢うて裁(わずか)に一問すれば
旧によって可怜生』
この詩の意味するところを意訳する。前段は「托鉢の道々、周囲の様子を見ると、農夫は田畑を耕し、農婦は織物を織って暮らしを立てている。ところで釈迦の子と称する僧は修業を積むわけでもなく、悟りをひらくのでもない。村人から施しを受け、食にありつき、人を集めて大口を叩き、農家の婆さんたちを迷わせている」というものであり、後段は「行脚に出ていく僧について思うには、一見、利口そうには見えるが、全ての僧がしていることは、禅宗の名高い三つの寺を訪れ、そこで座禅を組み、問答をしなければ禅僧としての資格がないとでも思っているようである。ここで交わされる問答は決まりきった筋書き通りの形だけのものである。こうした僧に会って、ちょっと問いかけてみると、師から教えてもらったことを言うだけの薄っぺらな僧であることがすぐ判ってしまう」という禅僧の日常の修行生活に対する批判である。しからば、己はどうかと顧みた時、良寛自身にも純粋さと裏腹の脆弱さや引っ込み思案という忸怩たるものがあり、自己の不甲斐なさと途方もない道の困難さに、「懶(ものう)く」思っていたのではないか。
『少年父を捨てて他国に走り
辛苦虎を描いて猫にもならず
人あって若し筒中の意を問わば
これはこれ従来の栄蔵生』
良寛栄蔵は、前回も書いたように橘屋、名主の跡取り息子であった。父、以南が橘屋を支え切れず、結局は隣町の京屋から追い落とされていく運命にあったが、名主見習いとして勤めた僅かの期間にも栄蔵にその才はなく、「昼行灯」と馬鹿にされ、橘屋から逃げ出したのである。名主などとても勤まらぬ自分の弱さを痛感したのだろう。悶々として四年間を光照寺で過ごしたと思われる。勿論、得意とする読書や漢詩つくりでは上達しても、心の晴れることはなかった筈である。
円通寺の国仙和尚が光照寺に立ち寄ったのが好機会となり、国仙和尚の人柄に魅せられて弟子にしてもらい備中まで付いて行った。そこから本格的な修行が始まり、師から曹洞宗の始祖道元禅師について教わった。僧として日夜勤めながら、五百年も前に始祖の著した「正法眼蔵」を、目を皿のようにして読み吸収したに違いない。だが読めば読むほど、その言わんとするところを理解すればするほど、良寛が感じる現実の僧の世界は、前記の漢詩「僧伽」の如きものであり、だからといって僧の世界の堕落と汚れを憤ってみても、「己に曹洞宗を回転させるだけの力量ありや」を自問自答したとき、良寛は頭を垂れるだけではなかったか。上述の短い漢詩はそんな良寛の心を嘆じたものだと思う。「父や家を捨てて備中まで来た。優れた僧になるべく修行もした。しかし、残念ながら落第生で終わってしまった。人から、もしお前は結局どうなったのかと聞かれれば、ただただ元の栄蔵のままですよとしか言えない」というのも悩みの一つであったと思う。
余談になるが、水上勉と吉本隆明は1982年7月に、雑誌「墨」の企画で、「仏教者良寛をめぐって」という表題の対談をしている。それが吉本隆明の良寛本には収録されていて、「野面(のづら)ゆく行乞の思想」という副題がついているように、良寛が僧の世界に馴染めずに、「僧は修行の末に寺の住職になる」という生涯ではなく、一所不住、托鉢、行乞の生涯を選んだ良寛の考え方の底流を、吉本隆明と水上勉がそれぞれの考えを披瀝し合って、探し求めた。吉本は水上の「蓑笠(さりゅう)の人」(1975年、文芸春秋社
発刊)を読んで水上の真意を探り、水上は吉本の「僧としての良寛」(1982年、「海」に掲載)を読んでの対談であった。
この対談で、水上は、吉本が近藤万丈の「寝覚の友」から、良寛の持っていた荘子本二冊について、「すでに良寛は道元の正統禅から荘子の世界へ脱化していた」と推論していることに驚き、吉本は、水上の「制度が厳しければ厳しいほど(封建社会のような)、無言の草莽の人間が地平におり、地平の有難さを知るこの人達のまなざしを忘れていても歴史は語られるが、十全ではない」という説に、良寛のもう一つの姿が見えたと感じた。両者に共通していた良寛は、「村という共同体の中で、村民の苦楽を自らの苦楽と感受しつつ、村民に融合し、村民からも認められ、一人の仏者として新しい世界に踏み出していた」ということであろう。集団として権力闘争のある僧の世界、制度の中の僧の在り様、これらに異質なものを感じ、懶くなる以上、良寛は独自の、一人の仏者としての道を拓いていかねばならない。山中の草庵に独居する。只管打坐(しかんたざ)し、行脚托鉢(あんぎゃたくはつ)に明け暮れる新たな生活、好きな漢詩づくりや書を続ける生活を拓かねばならない。もう一つこの対談から見えてくるのは、引っ込み思案、脆弱な良寛からの脱化であったとも応援団子には思われる。
まだまだ良寛の悩みを探るところまでには到らない。良寛の故郷越後への帰還のことである。四年間の放浪行脚のうちに良寛にもう一つ大きな悲しい出来事が起こっている。父、以南の桂川への入水自殺のことである。勤皇派の以南が幕府筋から咎められて、自殺を装い実は高野山に身を隠したとの噂があり、良寛が高野山に赴いたことは前回も書いた。これは現在に至るも謎のままで、正確な立証は為されていない。そして、父の死と共に気になるのは、自分が放棄し、弟、由之の継いだ橘屋の運営のことである。故郷から聞こえてくる話で、橘屋がうまくいっていないことは知っていたであろう。配下の百姓から代官所に訴えられるという危機も前後して起こるのである。覚悟を決めて良寛は故郷に帰ることを決意したと思われる。
『故郷へ行く人あらば言づてむ今日近江路をわれ超えにきと』
という短歌がある。応援団子には、上述のような事情に対応した良寛が覚悟して、いよいよ故郷越後に帰ろうとした決心が、この歌ににじみ出ているように思えてならない。
誰しも生きていくことは容易なことではない。殆どの人がそれぞれに、間違いなく何がしかの悲しい事情を抱えて悩んでいる。良寛は、そうした物事の「是非」や、「善悪」や、「真実か虚妄か」の本質がどこにあるのかを考え、考えた末に、それらの基準や根拠が実はあやふやなものであり、己の心に起因するものであるという考えに到達し、「それらに囚われてはならない」と、すべてを捨てることにしたのである。そして、良寛は始祖道元の教える「菩薩四摂法」の「布施」、「愛語」、「利行」、「同時」の中に自分の道を見つけたのだと思う。「四摂法」についての検討は次回に回すことにするが、おそらく良寛は窮極のところで、「己が苦しむ人のために出来ることは、その人と同じ目線でものを見、同じ位置に寄り添い、その人に優しくある」との着地点に到達したのではないか。良寛の「戒語」の中に「しみじみと語れ」というのがある。これは始祖道元の言う「愛語」を解した言葉であり、良寛は生起してくることは天真に任せ、「世間に身を晒す」ことにより、国上山五合庵の中に共同体の一員としての場を獲得したのだと思う。次回にこれらについて触れていきたい。また、吉本隆明が注目した水上勉著「蓑笠の人」について取上げることは出来なかったが、この作品も味わいたい。(応援団子A)
|