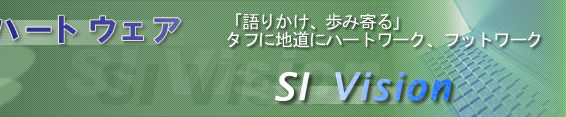子供のときに読んだ雑誌や絵本などで見る良寛さんは、村の子供たちとの手毬つきやかくれんぼなどを、時間も忘れて夢中になって遊んだ天真爛漫なお坊さんという印象で、大人になってもその印象は変わることもなく、その後もとくに良寛さんについて関心を持つ機会もなかった。ずっと後になって、といっても、もう30年くらい前になると思うが、「良寛さんをよく読め」と、師から植野明磧著の「良寛さん」をいただいた。この本は、良寛さんの純朴な人柄と真に人を思う心のことが書かれているが、何といっても「戒語=戒め言葉」に尽きると思う。「ことばの多き」、「はなしの長き」、「てがらばなし」、「じまんばなし」、「人のもの言いきらぬうちに、もの言う」、「人の話のじゃまをする」、「ことばのたがう」、「たやすく約束する」、「このんで唐(から)言葉をつかう」、「人に物くれぬうちに、何々やろうという。」、「くれてのち、人に語る」「酒に酔いてことわり(理屈)いう」「よく心得ぬことを人に教える」などなど、師は、応援団子の無思慮で雑な言葉使いを気にかけて下さり、「これをよく読め」ということだったのだろう。今でも亡き師の顔と一緒に思い浮かべて、戒語の一つひとつを自らに問うことがある。
もう二十年くらい前の話になるが、三年間ほど単身赴任をした。その頃に応援団子自身の中で猛烈に良寛細胞が騒いだことがある。水上勉の「良寛」本を読んでいたとき、夢の中に良寛禅師が出てきたのがきっかけであった。墨染めの法衣に手甲、脚絆をつけた托鉢姿の良寛禅師に対面した。応援団子は何かしきりに訊いているのだが、ただ、にこにこと笑顔で腰を折りながら、後ずさりをしていく良寛禅師の手は、顔の前あたりで「こちらにくるな」と制止しているようであり、僅かに左右にゆれて「そんなことに答えられない」と、後ろへ後ろへと灰色の雲の中に小さくなっていく夢であった。それからしばらくして吉本隆明の「良寛」本を読んだ。水上勉との対話が載っていた。これでまた良寛の輪郭が少しはっきりし、良寛禅師に一歩近づいた気がした。その後、同じような夢をもう一度見た。師を亡くした後のことであったと思う。後ずさりしていく墨染めの法師が師の顔になっていた。師と良寛は応援団子にとっては切り離せないところにある。さら
にもう一つ思い出すことは、生前の師に、吉本隆明の「良寛」の話をしたら、「まだ少し早いかな」と笑っておられた。あれはどういうことだったのだろうか。もうあれから十三年が過ぎた。
しばらく眠っていた我が良寛細胞が、ぱっと目覚めたのは昨年(2004年)7月のことである。パソコンを愉しんでいる読書好きの人にはご案内のことと思うが、松岡正剛がインターネット上で、自薦の千冊本を紹介しているサイト「千夜千冊」(2000年2月23日の第一冊目を中谷宇吉郎著「雪」で始め、昨年7月に四年数ヶ月を経て、ちょうど千冊目を披露する時期を迎えていた)を「良寛」で締めくくった。7月、真夏だというのに「外は、雪」になぞらえた自著の「外は、良寛。」も紹介し、「雪」にはじまり「雪」で閉めるという、まさに「雪結び」にした。
――松岡の「千夜千冊」の力作は今も続いており、その後、松岡は胃癌摘出のため入院、しばらくは中断したが、再び一千一冊目から紹介を始めて、現在は一千二十八冊目のジュリア・クリスティヴァ著「恐怖の権力」が紹介されている。
松岡は「外は、良寛。」(芸術新聞社1993年出版)の中で、良寛の作歌「淡雪の 中にたちたる三千大千世界(みちあふち) またその中にあわ雪ぞ降る」をとりあげ、「雪の空を見上げていると、次から次へと雪の中から雪があふれてでてくるように降り、これを眺めているうちに、大宇宙も小宇宙もこん然一体となり、良寛自らも雪と一体になっていく名状しがたい様子になったことを歌っているのだ」と、「十年以上前の作品だが、今でも気に入っている」とある。前述のように応援団子が当時熱中して読んだのは、水上勉や吉本隆明の「良寛」であり、そこに紹介されている吉野秀雄や唐木順三の「良寛」で、歌の解釈が進んだし、瀬戸内寂聴の「手毬」にも感動した。「外は、良寛。」は今回、この稿を書くので読んだ。
良寛禅師の生涯を、唐木順三著「良寛」(ちくま文庫本)、末尾の概略年譜などから写しておく。良寛は、宝暦八年(1758年)越後出雲崎の名主(屋号は橘屋)役の山本家に生まれる。幼名は栄蔵といい、父は以南(俳号)、母秀子の二男(長男は早世)で、弟妹は後に家を継ぐ由之ほか六人いる。十一歳(明和5年)大森子陽の塾に通い五年ほど漢籍を修める。父に代わって名主見習を勤めるも「昼行灯=ひるあんどん」などと蔑まれ名主には適せず。
十八歳(安永4年)
禅宗光照寺に最終的には逃げこんで剃髪をする。大愚良寛と称する。僧になって禅を学んだのではなく、禅を学んだ後に僧になったとある。
二十二歳(安永8年)
国仙和尚に随い備中玉島円通寺に赴き、以後三十四歳まで十二年間を円通寺で修行。この間、二十六歳の時に母秀子を病で亡くす。
三十四歳(寛政3年)
師の国仙和尚が入寂。円通寺を出て三十七歳まで諸国行脚をする。この頃、高知土佐を行脚中に近藤万丈と会ったか、「寝覚めの友」に了寛の名が残る。
三十八歳(寛政7年)
父、以南が京都で入水自殺を図ったか、あるいは韜晦して高野山に隠れたという。法要を済ませて越後に帰る。
三十九歳(寛政8年)
国上を中心にして住み、翌年から五合庵に寓すること十八年。
五十三歳(文化7年)
弟、由之(橘屋名主)事件あり、家財取上げ、所払いの処分を受ける。亀田鵬斎(江戸)が五合庵に良寛を訪ねる。この少し前に子陽塾の旧友三輪左一、田沢有願を相次いで亡くす。
五十六歳(文化10年)
「万葉集略解」を参考書として阿部定珍所有の万葉集に振り仮名をつける。
五十九歳(文化13年)
五合庵を去り、乙子神社境内の草庵に移り、ここで十年を暮らす。
六十九歳(文政9年)
この年初冬、三島郡島崎の木村元右衛門方の草庵に移り、ここにて死す。その間貞心尼と出会い、多くの交換歌を残す。
七十三歳(天保1年)
老衰、痢病にかかる。十二月から貞心尼が来て看病する。
七十四歳(天保2年)
正月六日島崎にて没す。「うらをみせ おもてをみせて ちるもみじ」が辞世の句という。
上述の如く、玉島円通寺の国仙和尚を師として十二年の禅修行に励んだことで、良寛の生涯は大きく変わった。ただ、僧ながら寺も持たず、佛者としての立身よりも「書」と「歌」に秀で、乞食(こつじき)をしながら、歌人としての道を歩んだといった方が分り易い。国仙は自身の死期の近いことを覚り「良や愚の如く道うたた寛し。騰々任運誰か看ることを得む、為に附す山形爛藤の杖、到る処壁間午睡の閑。」という詩偈を与えた。この詩の意味するところは、「良寛よ、お前は一見愚者のようにみえるが、いまやお前が得た道は、どう転んでもゆるがぬひろい道だ。お前の到達した任運騰々の境涯を、いったい誰がふかくのぞくことが出来るだろう。私はお前の今日の大成を祝って、一本の杖を授けよう。ありふれた自然木の木切れにすぎないが、今日からお前はこの杖を大事にしなければならないものだ。さあ、どこへ出かけてもよい。到るところにお前の世界がある。どこでもよい。お前の部屋の壁にでも立てかけて、昼寝でもするがよい」(水上
勉著「良寛」からの抜粋)というものである。水上によれば国仙和尚もよく旅に出た修行僧で、良寛に対しても詩偈として、「お前も修行僧として、諸国好きなところへ出かけて、己を磨け」と、寺に住むよりも諸国行脚が良寛には適しているとの判断だったのではないかという。
水上勉自身が幼児期から禅宗臨済派の相国寺に引取られて修行の経験者であり、水上本には禅宗の始祖達磨から数えて六代目の慧能が宋祖として選ばれるときの事情について興味ある物語や日本の禅宗の始祖道元の入宋時の体験、白隠禅師と正受との師弟の問答、他力宗派といわれる浄土宗派の様子など詳しく紹介されているが、仏教が持つあやうい性格の部分についてはここには書ききらないので、これは水上本に委ねることとして、良寛が円通寺に来てからの修行に対して、水上は師、国仙と良寛の間に、上述の五代宋祖、弘忍禅師と六代宋祖慧能の逸話や道元の入宋時の体験の中に似たような修行経過があったことをほのめかす。これはまた後述したいが、先ずは、後に円通寺時代を思い起こした良寛の次の漢詩を味わっていただきたい。
仙桂和尚は真の道者
黙して作し言は朴なるの客
三十年国仙の会にあって
禅に参ぜず経を読まず。
宗文の一句だに道わず
園菜を作って大衆(だいしゅ)に供養す
まさにわれこれを見るべくして見ず
これに遇うべくして遇わず。
ああ今これに放(なら)わんとするも得べからず
仙桂和尚は真の道者。
良寛が修行中の玉島円通寺に仙桂という人がいたが、「その仙桂和尚こそ真の道者である。参禅もせず、経も読まず、宗文の教えの一言とて口にせず、国仙和尚の下で三十年も働いたが、ただ畑で野菜を作りみんなに喰わせていた。自分はこの兄弟子を見ていて、本当は何も見ていなかった。遇うていながら遇うていなかった。今更これに習おうと思っても手遅れだ。仙桂和尚こそ佛道を会得した人だった」という意味になると思う。
水上は、相馬御風著「良寛百考」の中から国仙と良寛との問答を引出し、良寛が師に家風を問うたところ、「一に石をひき、二に土を運ぶのだ」と、「人間は朝な夕な何かをして喰わねばならぬ。座禅、礼拝、読書も必要だが、一にも二にも手を汚し労働をすることだ」という答えを提出している。学問として、知識として頭に経典を叩き込む修行よりも「一日不作、一日不喰」という、始祖道元が宋の天童山で体験したこと(座禅にも、提唱にも行かず、ひたすら炎天下で椎茸干しに精励する老下働きの姿に感動する、典座教訓といわれるもの)を、言って聞かせていたのではないかという。ただ、良寛に畑仕事をする能力はあったのだろうか。これがまた良寛の悩みになっていたのではないか。
このほか、水上が玉島で聞いた話として一つの「良寛逸話」を提供している。これは良寛が乞食のような姿で村の子供と遊んでいるのを、村に盗難事件があって盗人を取り締る役人に怪しまれ、良寛は捕まえられたことがある。「お前が盗んだのであろう」と言われ、良寛は名も名乗らず弁解もしなかった。引き立てられていくうちに、名主風の男が通りかかり、良寛のおちついた態度に感心して、「なぜ、役人に名をいい、弁明しないのか」と聞いたところ、良寛は「人から見れば、自分に疑われるようなところがあるのだろう。それを反省して、自然に任せようと思ったのだ」と。普通の人間が出来ることではない。またそのほかにも農家の壁にもたれて居眠りをしていて、これも怪しまれ掴まったことがあるらしいが、このときも弁解せず役人に引っ張られていったという。水上はこうした逸話の中に、当時の良寛がより鮮明に見えてくるのではないかという。
円通寺に来たってより幾回か冬春を経たる。
門前は千戸の邑、すなはち一人だに識らず。
衣垢づけば手ずから濯い、
食尽くればじょういんに出づ。
かつて高僧伝を読むに僧可は清貧を可とす。
(意訳)
円通寺に来て何年経ったであろう。
門前には千戸ほどある村だが、知っている人は誰もいない。
衣服が汚れれば自分で洗い、食べ物がなくなれば町へ出て托鉢している。
高僧伝にあったが、慧可大士は清貧に甘んじるがよいと言われた。
円通寺時代の良寛はまさしくこんな生活を送っていたのだ。師の国仙和尚を通して道元を習い、道元を読んだ。ところが仏教を極めれば極めるほど、修行と僧生活の実態の差が良寛には見えはじめ、敷かれた制度に身をおくことは出来ないと懊悩していたと思う。国仙和尚もこれに気がつき、上述のような詩偈を授けることになったのではないか。円通寺を出た良寛は、四年に近い行脚をし、父の死に出会い、それは偽りで高野山に隠遁したのではないかとの噂が流れれば高野山にも赴いた。だが何か期するところがあって越後出雲崎に帰る決心をするのであるが、良寛の心中を吐露した多くの詩がある。が、これらは次回の稿に回すことにし、今回はもう一つだけ漢詩を紹介して擱筆することにする。
生涯、身を立つるに懶(ものう)く
騰々、天真に任す
嚢中、三升の米
炉辺、一束の薪
誰か問わん、迷悟の跡
何ぞ知らん、名利の塵
夜雨、草庵の裡
双脚、等閒に伸ばす
上述の漢詩は、良寛の托鉢、乞食(こつじき)に徹した生涯を最もよく言い表したものであると、唐木順三は自編「良寛」の中心題材として説明する。「身を立てるべく生涯を過ごしていくのは面倒なことだから、ただただ自然のあるがままに任せることにする。頭陀袋の中には三升の米が入っており、炉辺には一束の薪がある。誰かから迷いや悟りがどうだと言われてもそんなことはどうでもいい、名誉も栄華も塵のようなもの。草庵に夜雨が降りかかってきても両足をユックリと伸ばして一日を終えるのみ」と。この歌は良寛も気に入っていたようで、幾つかの場所に書き残しているようである。前述の如く、結果として良寛は寺を持たず、さりとて人里を遠く離れて隠遁したわけでもなく、子供と戯れ乞食に終始し、厳しい江戸後期の越後の五合庵に自らを晒した清貧の生活を選んだのである。(応援団子A)
参考著書
一、 植野明磧著「良寛さん」(柏樹社 1974年 初版発行)
一、 水上 勉著「良寛」(中央公論社 1984年 再版発行)
一、 吉本隆明著「良寛」(春秋社 1992年 第一刷)
一、 唐木順三著「良寛」(筑摩書房 1992年 第三刷 ちくま文庫)
一、 松岡正剛著「外は、良寛。」(芸術新聞社 1994年 第三刷)
一、 吉野秀雄著「良寛」(アートデイズ社 2004年版)
この本は、筑摩叢書 1975年版の復刻版である。
|