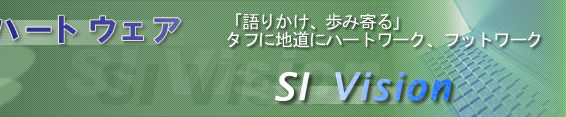『「さっきの書付はどうしたい」 「箪笥のひきだしにしまって置きました」
彼女は大事なものでも保存するような口ぶりでこう答えた。健三は彼女の所置を
とがめもしない代わりに、ほめる気にもならなかった。
「まあよかった。あの人だけはこれで片が付いて」
細君は安心したといわぬばかりの表情を見せた。
「何が片付いたって」
「でも、ああして証文を取って置けば、それで大丈夫でしょう。もう来る事も出
来ないし、来たってかまい付けなければそれまでじゃありませんか」
「そりゃ今までだって同じ事だよ。そうしようと思えばいつでもできたんだから」
「だけど、ああして書いたものをこっちの手に入れて置くとたいへん違いますわ」
「安心するかね」 「ええ、安心よ。すっかり片づいちゃったんですもの」
「まだ中々片づきゃしないよ」 「どうして」
「片づいたのは上部だけじゃないか。だからお前は形式ばった女というんだ」
細君の顔には不審と反抗の色が見えた。
「じゃどうすれば本当に片づくんです」
「世の中に片づくなんてものはほとんどありゃしない。一ぺん起こった事はいつ
までも続くのさ。ただいろいろな形に変わるから人にも自分にもわからなくなる
だけの事さ」
健三の口調は吐き出すように苦々しかった。細君は黙って赤ん坊を抱き上げた。
「おおいい子だいい子だ。お父さまのおっしゃる事は何だかちっともわかりゃし
ないわね」
細君はこう言い言い、幾たびか赤い頬に接吻した。』(「道草」百二 最終部)
上述に掲げた文は、夏目漱石著「道草」最終章百二の最終部である。「道草」は漱石晩年の著作の一つで、大正四年六月から九月まで朝日新聞に連載された。この作品は明治三十九年から四十二年まで足掛け四年間に亘って、自らの生い立ちの複雑さと父親夏目小兵衛直克の復籍処理の杜撰さから、自分自身ではどうしようもない養父母との暗い繋がりを思い起こさせ、本来縁の切れていた筈の養父から「身寄りのない年寄りを放っておくのか」と、お金をせびられる嫌な出来事を、兄や義兄に斡旋して貰い調停していった過程を小説にしたのである。それにしても明治四十三年四十三歳から大正五年四十九歳で亡くなるまでの漱石年譜を見るだけでも壮絶な晩年の様子が窺える。胃潰瘍による大吐血と再発の連続、痔疾手術、ひっきりなしに続く神経症で、病臥、入退院、転地療養を繰り返している中で、妻に喚き散らし、絵を描き、良書を求め、執筆したのである。「道草」に先駆けて同年一月から二月にかけて執筆し
た「硝子戸の中」は、淡々と日常の生活を述べ、過去を振り返っているが、読み方によっては、死期を意識した自伝とも考えられる。そして、間違いもなく「道草」の予告編の役割を果たしており、併せて読まれることを薦めたい。
先ずは小説「道草」の筋書き説明のためにも、その「硝子戸の中」と、江藤淳著「漱石とその時代」(第一部)から漱石の生い立ちを抜書きしておきたい。漱石は慶応三年(1867年)二月九日父直克五十歳と母千枝四十一歳の間に、末っ子の五男坊として江戸牛込馬場下(現在の新宿区喜久井町)に生まれた。誕生日が庚申の日で、この日に生まれた子は大泥棒になるとの祟りを恐れ、厄除けに「金」の字を入れて金之助と命名された。直克には先妻こととの間
に佐和と房という二人の娘があり、夭折した四男久吉、三女ちかを除いて、漱石は二人の姉と三人の兄を持つ。夏目家は代々牛込馬場下一体の町方名主(現在で言えば区長くらいか)を勤める家柄で、父直克も当初は羽振りも利いたのだろうが、何せ金之助が生まれた頃は明治御一新の前夜、幕府瓦解の年であり、さすがの名主も身分を奪われる恐怖に苛まれていたと思われる。金之助は生まれて日時も経たないうちに、四谷大通の古道具屋に里子に出され、夜になっても店先の笊(ざる)の中で眠っているのを姉の房が見つけ、「これではあんまりだ」と抱き上げて連れて返ってきたが、二歳になって今度は名主仲間の塩原半助の跡取りで、直克が後見人になっている塩原昌之助、やす夫妻の養子に出された。
事のついでに夏目家の家族のことについても抜書きしておく。一度は出戻った長女佐和の嫁ぎ先は、継母千枝の実家筋に当たる好きだった福田庄兵衛のもとへ、次女の房は直克の弟が継いだ高田家の跡取りで、房にはいとこになる庄吉のもとに嫁いだ。千枝の子供達は金之助を除いて、跡継ぎの大助はじめ三男までは病弱ながら放蕩揃いである。
大助は陸軍省の翻訳係をしていたが結核で挫折し三十一歳で亡くなる。二男の栄之助は父親の希望もあり、初代夏目直克の実家である臼井家の養子となり、通信技師として地方勤務をするうち、岡山で見そめた片岡かつと結婚するが、大助没後三ヶ月、結核で追うように逝った。三男和三郎は前出の庄吉と佐和の養子となったが三年ほどで戻り、以後夏目の家でぶらぶらしていた。これは後の話ではあるが、遊び人和三郎の嫁、嫂の登世こそ金之助が密かに恋心を抱いたその人である。それはともかく、金之助が小学校在学中に、養父塩原昌之助が連れ子を持つ日根野かつと懇ろになり、やすは家を出ていくし、金之助も祖父母と思い込んでいた実父母と、病弱な兄三人との生活が待つ夏目家に戻る。ここで直感的な喜びを得たようではあるが、本来の家庭愛には程遠く、十数年間を塩原姓のままで暮らした。
夏目家に帰って来た金之助が、ある日座敷で寝ていると枕もとで小さな声で呼ばれ、暗い中をよく見ると、下女が「あなたがお爺さんお婆さんと思っている方が、本当のお父っあん、おっ母さんですよ。お二人がこっちの家が好きなのはそのせいだろうと言っていたのを聞いたから、そっと貴方の教えてあげるのですよ。誰にも話しちゃいけませんよ」と耳元で囁かれ、「誰にも言わないよ」と答えたきりだったが、心のうちでは大変嬉しかったと心情を吐露しているし、また、二階で昼寝をしていて夢の中で、身に余る金を使ってしまって処置に困り、大声で母を呼んだらすぐ二階に上がって来てくれたので、「助けて下さい」と言ったら、ニッコリと笑って「心配しないでいいよ。おっ母さんが幾らでもお金を出してあげるから」と言ってくれ、安心してすやすやとまた寝てしまったと書き、それが現実であったのか、夢の出来事なのかははっきりしないが、母の服装がいつも母の着ていた着物と帯びであったとも書いている。「硝子戸の中」に、淡々と真情を披瀝する漱石の求めていた家族愛への憧憬というか、渇望している思いが伝わってくる。長じて家長としての漱石が、鏡子夫人との間で求めた現実の家族愛では、空回りに終わることが目に付く。
金之助少年は頭脳明晰であったが、小学校時代は家庭のいざこざがもとで、中学校では儒教中心か英語中心か教育方針が定まらない中で転校を余儀なくされ、明治十七年入学していた神田一ツ橋の大学予備門が改称されて第一高等中学校となり、腹膜炎を患って落第するが、同じく落第した終生の友となる中村是公(後に満鉄総裁になる)と江東義塾の教師をしながら学費を稼ぎ、学業に励んで以後は首席を通した。この時期、若者はお国のために役立つ「有用の人」になることを求められており、金之助も将来の選択に悩む。金之助の優秀なことを認めていた長男の大助は、大学学科選択の折、「文学は職業にならない」と文学に憧れている金之助を牽制し、金之助もこれに従って建築科しようとするが、哲学を志望する同じクラスの賢友米山保三郎に「今から建築を学んでも西洋に勝るものが出来るのか」と叩かれ、あっさりと心底で考えていた文学に変えてしまった。余談ながら、大助は金之助に夏目家の跡目を継がそうと考えたが、これは金之助が断って実現しなかった。前述のように、金之助は二十歳の時、大助も二男の栄之助も結核で早世した。翌年、直克は二十一歳になった金之助にようやく夏目姓に戻るように指示した。
金之助も「それならば」ということで、夏目家に帰ってから十数年間を経て、ようやく塩原姓から夏目姓へ帰ることになり、七十歳になっていた直克は金之助復籍のために、塩原昌之助と証文を交わして、金之助の二歳から九歳までの養育費二百四拾圓を支払う約束をした。実際には百七拾圓を一括して支払い、残金七拾圓は割賦の月払いにした。
問題はその証文の中で、塩原昌之助はさらに金之助に対して事後の関係が不実不人情にならないようにと書かせた。この背景には上述の養育期間七年に対し、塩原昌之助の方では十五年と考えており、直克は、金之助と直接交渉をして「不実不人情にならざること」と、金之助から一筆を取った塩原昌之助を怒り、絶交を言い渡したが、結果として塩原昌之助は二百四拾圓で決着させず、絶交の代償とでも言うべきか、成長した金之助からさらに幾らかの金額を支
払わせる権利を保留したことになる。こうした状況が、後々「道草」の材料になる問題の核心であった。金之助の方でも夏目の家に帰った後も、塩原昌之助とかつの新家庭に行き来して食事もしたり、かつから小遣いを貰ったりしていたことも事実のようであり、かつの連れ子れんとの淡い恋心くらいは芽生えていたのかも知れなかった。
金之助については、東京帝国大学文学部英文学科を卒業し、後に文部省命で英国に留学して経験した苦悩も触れたいし、結婚のことも省略した。後に金之助が使うことになった「漱石」という雅号を考案し、教師として出向いた松山では起居を共にしたことのある正岡子規のことについても書きたいと思う。また、若い時からの神経症に悩まされながらの、漱石としての文筆活動についても考察を続けたいのもやまやまではあるが、ここでの趣旨にそぐわないので省略することにしたい。
晩年の漱石である。頭を悩ませた神経症は、妻の鏡子を巻き込んで更に壮絶さを増していくことになる。「道草」の健三が、兄と義兄の協力を得て、ようやく元の養父島田から証文を取って、細君が「これであの人のことは片が付いた」と喜んだ時、「何も片付きゃしない」という健三の心のうちには、「硝子戸の中」(三十)で、訪問者の見舞いに対して「病気継続中」と答える漱石の心情である「継続中のものは恐らく私の病気ばかりでなく、全ての人々の心の奥には、私の知らない、又自分さえ気の付かない、継続中のものがいくらでも潜んでいるのではなかろうか」という叫びがあり、「所詮我々は自分で夢の間に製造した爆裂弾を、思い思いに抱きながら、一人残らず、死という遠い所へ、談笑しつつ歩いていくのではなかろうか、唯どんなものを抱いているのか、他人も知らず、自分も知らないので、仕合せなんだろう」という気持ちになっているのである。ただ、細君が「お父様の言うことはちっとも分かりゃしない」と、夫を理解せず、子供に逃げていく態度にこそ、漱石が求めながら捕まえることの出来なかったものではないかと思う。突き詰めて言うなら「どうあがいてみても人の一生は悲しい」ということか。
数年前に「夏目漱石悲しい音」と題して一文を寄稿したとき、「吾輩は猫である」の最終章から猫の独り言として語られる「呑気に見える人々も、心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする」というフレーズを挙げたことがある。漱石にとっての「悲しい音」とは、外部には黙っていても、外部からは見えなくても、実家、義兄の所、妻の実家への支援を常に想定して、親類縁者の「活力の中心」として働かねばならず、喩え書付を取り込んでいても、どう変化するかも知れないし、生きている以上、心の底にある邪悪なもの、不安なものから逃れることが出来ず、死ぬまで続く「耳鳴り」のようなものであったと思われる。現代では、流行ことば「リセット」が言われる昨今、世の中では人々の行動において、「リセットをよし」とする風潮なきにしもあらず、こんな風潮はどう考えても良い訳はなく、「人生のリセット」など出来ない。現代人は、漱石の真似は出来ないにしても、「継続中」について、もう少し悩む必要があるかも知れない。(応援団A)
|