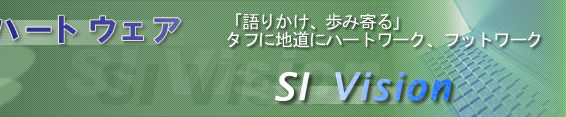|
新年明けましておめでとうございます。本ホームページをご訪問いただきました皆様方の益々のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。併せて応援団子に対しまして、本年もよろしくご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
小学館の昭和文学全集「遠藤周作」年譜を見ると、著者は1974年秋に、支倉常長の行跡を辿る一ヶ月ほどのメキシコ旅行をしている。この小説「侍」(1980年初刊)を書くために、常長の見た情景を自らの目で確かめたのである。別著「人間の中のX」(中央公論社、1978年)には、その取材旅行を「悲劇的な人物の伝記ではなく、彼の生涯を踏み台にして小説を書くことだった」とある。支倉六右衛門常長(はせくらろくえもんつねなが)とは、1613年、藩主伊達政宗の命により、商人を含む総勢150名程の遣欧使節団長としてメキシコからスペインに渡って国王に会い、さらにはローマまで行って法王にも会った貴重な日本人ながら、1620年に伊達藩に帰り着いた後、僅か二年にして没した侍である。伊達藩には常長の行跡を記述した資料も日記も残っておらず、この壮挙を果たした男の生涯はまさに悲劇的であったのである。先ずはその背景を探ることにする。
前年、紀州沖でイスパニア(後のスペイン)船が難破して、30余名の船員が救助されたが、船が修復不可能になっていたことが事の発端となった。この災難に目をつけた徳川家康は、スペイン船員を帰国させることを名目にして、遠洋航海が可能なガレオン船の造船技術と遠洋航海術そのものの習得を企図した。加えて、ノベスパニア(後のメキシコ)との直接交易の狙いもあって、伊達藩主政宗に造船とノベスパニア交易依頼文書を届ける使節団の派遣を持ちかけた。当時、ノベスパニアはイスパニアの統治下にあり、ノベスパニアだけの判断で交渉成立するとは考えられず、ただ、遠方の長崎ではなく、仙台からの直接交易が成功すればとの皮算用だけが先行した。二人の権力者にしてみれば、確かに日本国の経済構図を変える魅力的なものであっても、成功率が極めて低いこの冒険に、政宗は重臣とはいえない支倉常長を団長として派遣したというのが史実らしい。
当時、外国人の日本入国の主目的は、キリスト教の布教であり、彼らは美しいガラス工芸品、精巧かつ高級な調度品、或いは織物、葡萄酒など、進んだ文明から生まれた品々を武器にして大名にも近づいた。織田信長の時代には、信長は仏教徒との争いで頭を悩ませていたので、その対抗手段としてキリスト教を利用した。豊臣秀吉の時代も当初は交易振興を優先させ、キリスト教を黙認していたので、九州、京都を中心に信徒は増えていったが、1596年、「布教に日本支配の野心あり」との情報が流れて、秀吉は宣教師二十六人を長崎で磔刑に処した。徳川家康の時代になると、キリスト教の禁止は勿論のこと、鎖国までして長崎以外での外国との関係を閉じた。戦国時代の権力者たちは、宣教師達を情報収集や勢力拡大の手段と考えても、裏切ることに罪悪感など微塵もなく、宣教師達の方でも権力者の狡猾さを察知していて、双方で虚々実々の駆け引きがあったようだ。
いよいよ上述の文章に話を進めるが、物語の前後の「あらすじ」から始める。この小説では「侍」と書かれる長谷倉六右衛門と、その同志である松木忠作、田中太郎左衛門、西九助と数人の下男とが、幕府に捕縛されていたところを通辞として使節団に同行したベラスコ神父と共に、ノベスパニアのメヒコに到着したが、アクニア総督からは藩主の願いは聞き入れられず、松木忠作と商人達はこの地で日本へ帰国することになり、長谷倉、田中、西と下僕たち、それにベラスコ神父が、本国イスパニアの皇帝に念願するべく、大西洋側のベラクルスまでの険しい山道を進んでいる情景が上述の文章である。ベラスコ神父にはイスパニア行きは筋書き通りであったが、先が読めない長谷倉や田中には決死の山越えであった。巨大な山とはポポカテペトル山(標高5452米)のことで、まるで神の如く聳えるこの山が、小さな人間の諸行を見詰めているかような描写になっている。
同行している日本人を入信させ、この冒険を成功させて、日本におけるキリスト教司教になることを企むベラスコ神父の野心に、航海中から気づいた松木忠作は、先の戦で武功がなく、先祖代々の旧領を荒地にすり返られて、「再び旧領に帰して欲しい」と、機会があるごとに申し入れをする厄介者が、この使節団に選ばれたことを見透かしており、万に一つも成功すればというこの難業を、押し付けた藩主たちの考えも察知していた。松木忠作以外は「この使命を成功しさえすれば、元の豊かな先祖代々の知行地に」と、勝手に想像しているのである。松木は侍達に「そのような夢は捨て、自分で自分を守る以外にない」と説得したが、若い西九助は好奇心が先行し、田中も侍も惨めな環境から抜け出す気持ちが先行した。上述の文章で、侍が「松木の思惑など取るに足らぬ」とか「松木にはわからぬ世界」と、巨山に圧倒されての考えが湧いたとしても、さて結果は如何。
イスパニアで国王に会うことは出来たが、交易交渉には応じてもらえなかった。そして最後の望みを託すローマ法王の対応も同じだった。すでにイスパニアにもローマにも日本のキリスト教徒迫害の報は伝わっていた。侍たち三人が「お役のためなら」と入信までしての結果がこれであった。田 中太郎左衛門は切腹してこの地で果てる。やっと帰り着いた日本で、侍達を待ち受けていた運命はもっと過酷で、入信したことが罪になった。役人に連行されていく侍は、下男の与蔵の「ここから先はあの方がお供をなされます」との声に大きくうなずく。一方、挫折したベラスコ神父も、再び日本に密入国したが、捕らえられ火刑に処せられるところでエンディングとなる。ただ、著者はこの悲惨な終末を迎える侍には、「ここからはあの方がお仕えなされます」の言葉を、ベラスコに火の中で「生きた・・私は・・」と叫ばせ、それぞれの苦悶のうちにも安らぎを与えているのである。
遠藤周作は自己形成が出来ていない子供の頃に、伯母様の勧めでキリスト教に入信したという。後にその事に随分と悩んだとも聞く。この小説の中でも、ベラスコが役人に問われて、「侍たちはお役目を果たすために入信した」と説明した後で、「では」と役人に見据えられて「切支丹と申せぬのだな」と聞き返され、ベラスコが黙ってしまう場面を挿入している。著者はそこで「どんな形であれ洗礼を受けた者には、当人の意志を超えて秘蹟の力がはたらく」と書いて、読者には「入信という行為の尊厳さ」を伝える。正面から向き会ったことがない宗教を、応援団子は語る資格はないが、巻末に至って、人がたとえ過酷な死を迎える時でも、心静かに「安らかに逝く」ことを、これほどまでに読者に伝え切る思いは、著者の信仰心の深さ以外には考えられない。著者も長い懊悩の末に、「十字架に釘づけされた痩せこけた男」に帰依することを誓ったのだ。
読後、応援団子は著者から伝わってくる優しさに満ち足り、「神とは何か」、「人が生きていくとはどういうことか」についての思いを広げてみた。仏教に帰依していなくても日本人なら仏像の前では手を合わせるし、仏像の姿の静寂さからは、安堵の気持が自然に満ちてくる。神社を参拝すれば、日頃の健康を感謝し、これからの平穏安泰を祈ることは、日本人なら誰もがしていることと思う。祈る人の心には損得勘定など微塵もなく、生かされているという感謝の念からは、豊かで静かな心の平安が満ちる。宗教とは人の心を豊かな温水で満たすようなものではないか。閑静で穏やかで謙譲な気持ちを持続させてくれるものではないか。生きていくことに確固たるものを与えるものではないか。ところが現実の生活では、安らぎや暖かさを喪失したギスギスのリズム、合理的な割り切りだけを優先させて、よしとする軽薄な態度、気がつけば我執に囚われた愚かな日常がある。
別に特定の宗教を信仰することでなくても、生かされていることへの感謝、人を思いやる心、人間の尊厳を保持するためには痩せ我慢も、謙譲も、己の心がけ一つで、反省の時間を持つことは可能ではないか。いつかこの「書を学ぶ」でも採り上げたいと考えている新渡戸稲造著「武士道」の1905年、増訂第十版にグリッフィス教授の一文が緒言として掲げられており、そこにグリッフィス教授が1860年にフィラデルフィアで、江戸からの使者として日本人を初めて見、その使者達の礼儀正しさを、その後の三年間、彼らを教え、共に暮らして体感したとある。特に、 病に倒れ異国の地で死を迎えた武士の少年日下部が、死際にキリスト教入信を勧められた時、「よしや私があなた方の主イエスを知ることが出来たとしても、私は生涯の滓(かす)だけを彼に捧げることはできません」と答えたことを決して忘れないと書き、少年の臨終を芳しき花の香り喩えて称賛している。
グリッフィス教授は1870年には招聘に応じて来日、教鞭もとられ、越前福井で自分の目で見、身体に感じた茶の湯、柔術、刀の作法、長閑なる挨拶と丁重を極めた人々の物言い、妻、下婢、幼児のための任侠など、思想と生活の活きた学校として少年、少女も等しく訓練されていることは、まさに新渡戸博士の書かれた「武士道」の通りであると記されている。現在では、当時の武士道の総てを肯定するわけにはいかぬが、一つや二つの欠点を挙げて、それで全てを否定してしまう現在の風潮は抜きにして、日本人が本来誇りにしてきた儀礼、躾、作法など、嘗ての美風を再び実行することは出来ないのか。そこには伝来の日本人の宗教心が活きていると思う。(応援団A)
|