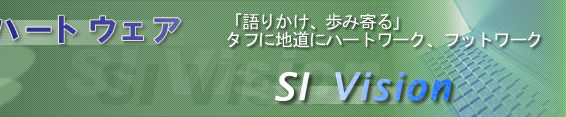| 今回は近代日本文学の先導者の一人、夏目漱石の著作「虞美人草」を取り上げたい。昨年は漱石が「坊ちゃん」を著して百年目にあたった。ちなみに、街行く人に「『吾輩は猫である』や『坊ちゃん』を書いたのはだれ?」と問えば、大体の人から「そりゃぁ夏目漱石だよ」と正解が返ってくると思う。では、さらに突っ込んで「じゃぁ、それを読んだ?」を問うと、何人の人が「ハイ」と返答できるのだろう。名作というのは作者の名前は承知していても、案外と読まれないものである。そこで今回は「吾輩は猫である」か「坊ちゃん」を書こうかとも思ったが、それではあまりにも芸がない。もう一歩踏み込んで、漱石が東京帝国大学を辞して朝日新聞に入社し、筆一本で生計を立てようと覚悟を決めた直後の第一作、新聞小説「虞美人草」を読むことにした。明治40年6月から10月まで連載された長編の作品である。
明治40年頃の日本といえば、日露戦争が終結して、人々が「西欧諸国に追いつく第一歩」を踏み出せたと思っていた頃であり、国家構造をより強固なものにしようと、山積する問題を急ピッチで、しかもかなり強引に処理していた時期にあたる。内には東京株式市場の相場が暴落したり、足尾銅山で暴動があったりと、困窮する人民の社会運動が目立ち出したし、外には韓国、中国への侵略を図るプログラムが動き始めた時期に当たる。まだまだ全般的には日本は貧しかったのである。また、別の面から捉えれば、たとえば「江戸っ子」の中に生きていた、ある種、誇りとされて来た「気概や人情的なもの」が内在化して、言わば「無恥厚顔」とされるものが表通りを歩き出した頃でもあった。
物語は、大学を卒業した後ブラブラしている東京の二人の男、宗近一(はじめ)と甲野欽吾が、京都に遊びに来ていて、比叡山に登る山道を行くところから始まる。この二人の家は比較的裕福であり、学校を卒業して二年にもなるのに、職に就かなくても食える状態にはある。四角い男、宗近一は、一年前は不合格であった外交官試験を再度受験し、合格の知らせを待っているところであり、細長い男、甲野欽吾は仕事を持たない神経衰弱気味の哲学者(漱石の小説にはこの種の登場人物が出てくることが多い)で、今回の旅行も甲野欽吾の衰弱気味な精神を癒すのが目的の一つであるらしい。
甲野欽吾には藤尾という美人の腹違いの妹がいる。藤尾は明らかに時代の先端を行く自我の強い女性で、読むに連れて判明してくるが、気位の高い、しかも激しい性格の持ち主である。二人の父親は海外で亡くなり、欽吾にとって継母になる母と藤尾と三人で暮らしている。亡くなる前に欽吾の父は、宗近一と藤尾が結ばれることを期待していたこともあり(外国に出発する前に、帰国したら自分の金時計を一にやると約束して出かけた。「藤尾が金時計を放さなければ、一緒に持っていけ」というようなことも言っていたのに、亡くなってしまった・・・。)、一(はじめ)は、外交官試験に合格すれば、藤尾との縁談を進めようと密かに思っている。一方、宗近糸子もまたしっかり者で、こちらは欽吾に好意を寄せている。だから物語としては、一と藤尾が結ばれ、欽吾と糸子が一緒になれば、ハッピーエンド、目出度し、目出度しということになるのだが、漱石は簡単にそうはさせないストーリーを準備していた。その一つを崩した。
京都から花の東京に勉強に来ている小野清三を漱石は登場させるのである。小野は頭脳優秀ながら、出身が貧しい家の出らしく、小さいときから学資を恩師の井上孤堂先生に出して貰い勉強を続けた。井上先生のおかげで東京に出てくることも出来、卒業時には成績優秀で銀時計まで賜った。先生には小夜子という娘がいて、密かに小野と小夜子が結ばれることを願い、それを信じて小野を支援してきた。小夜子もそのつもりでいた。今度、京都での生活にケリをつけ、娘ともども東京に出てくる決心をしたのもそのためだった。先生は小野に東京へ転居する旨の手紙を書いた。東京の小野清三はそれが疎ましかった。甲野藤尾に惹かれており、博士号と藤尾を一挙に得ようとしていたからである。宗近一に渡る筈の金時計を藤尾は小野の前で見せびらかせる。小野は藤尾もさることながら、その金時計、つまり甲野家の財も同時に手に入れるつもりになっている。
余談になるが、漱石の小説の場合、それが恋愛ものであるといっても、「惚れた、脹れた」が話の中心にならない。当人達と家族の経済(お金)や家柄(格式)や世間体(せけんてい)や面子(プライド)が微妙に絡まりついて、重苦しい様相を呈してくる。もっとも、必ず登場させる気難しい主人公も大いに関係してくる。さらにもう一つ、漱石の女性観は一筋縄ではない。後の著作「行人」でも取り扱われるが、「結婚すると、女性の持っているそれまでの性格が変わる。それも夫の立場からすると悪くなる」というものである。こうした女性観は夏目漱石の育ち方にあったと専門家は言う。何でも漱石は実母に優しくされた思い出は一度しかないというのを何処かで読んだことがある。
漱石はこの物語の中で、欽吾と藤尾の母の考えにも女のエゴを持たせた。自分にとっては実子ではない欽吾には家を出てもらい、藤尾に養子をとって自分の老後の安泰を図ろうと目論んでいる。その場合、亡き夫の選んだ宗近一のような二年越しの外交官よりも、銀時計組の小野清三の博士号を選ぶという描き方である。当時の女人の考え方として、明治維新の荒波を生き抜いてきた弱い人間の知恵として、漱石はいやらしいまでに女の業を書き尽しているではないか。勿論、宗近一よりも文学者小野清三に好意を寄せる娘の藤尾に対しても、漱石は厳しく見つめているのである。
先を急ぐ。この物語の終末は、言わばライバルの宗近一の説得(心からの諌言)で、藤尾に傾いていた小野清三は、人間として目が覚め、人間を取り戻し、井上先生の報恩、小夜子の愛に応えなければならないと考え始める。そして宗近が藤尾の前で小野と小夜子との結婚を説明する。そのときに藤尾の取った態度を漱石は次のように書く。「藤尾の表情は三度変わった。破裂した血管の血は真っ白に吸収されて、侮蔑の色のみが深刻に残った。仮面の形は急に崩れる。・・・」と。プライドを傷つけられ、高慢の面皮を剥がされ、ヒステリックに笑った忘我の藤尾は、小野の欲しがっていた父の形見の金時計を、宗近一に「あなたにあげましょう」と差し出す。それを宗近は暖炉の大理石に叩きつける。実に漱石の真骨頂である。翌日、藤尾は毒をあおって自ら死を選ぶ。
明治維新以後、日本の中に取り入れられた西洋式の自我と、江戸から続く武士、町民社会が形式的には崩壊したとはいえ、人々の内に燃えるいわゆる「日本的なもの」とのぶつかりの、一つの結果を漱石は書いた。藤尾の死後、甲野欽吾の日記に書かせた「道義に重きを置かざる万人は、道義を犠牲にしてあらゆる喜劇を演じて得意である。ふざける。騒ぐ。欺く。嘲弄する。バカにする。踏む。蹴る。――悉く万人が喜劇より受ける快楽である。(略)――喜劇の進歩は底止することを知らずして、道義の観念は日を追うて下る。道義の観念が極度に衰えて、生を欲する万人の社会を満足に維持しがたきとき、悲劇は突如として起こる。(略)万人の目は初めて生の隣に死が住むことを知る。・・・」を読み取るとき、これ以後、日本人が進んでいった破滅への道を、漱石は既に「危ない」と予感していたのだろうか。
知者が考え抜いて書いた作品には、ことに漱石の作品は、現在の我々が思いを新たにすべき問題が潜在していることは間違いない。我らの課題は「作品にちりばめられた言葉や行動を、今の世で、どのように読み取るべきか」なのだと思う。
(応援団子A)
(註)本作品は全集から文庫本まで出版社多数。よって出版書名は省く。 |