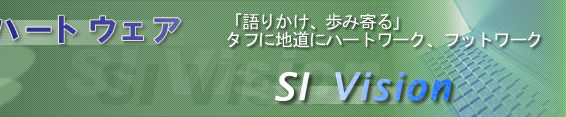元禄2年(1689年)芭蕉45歳の秋、蕉門の人たちが出迎える大垣に、敦賀まで迎えに出た路通と一緒に到着し、奥州路7か月の旅を終えます。その大垣では、早速に門人たちが準備していた句会の席が待ち受けていて、客人としての務めを果たしました。旅の疲れがまだ癒えたとは言えない15日後には、ふるさとの伊賀上野に向かって出立しています。芭蕉はこの後、足掛け四年の間は江戸に帰らず、京、滋賀湖南に滞在して、撰集「ひさご」や俳諧の古今和歌集と言われる撰集「猿蓑」の編集支援をしました。「ひさご」は、濱田珍碩(後の酒堂)が主になって元禄3年に纏め、1年後の元禄4年には、「猿蓑」全6巻を野沢凡兆と向井去来が纏めて、京の井筒屋で発刊させました。芭蕉には奥州路の旅の途中で、閃いていた「これからの俳句の在り方」についての論考を纏めねばなりませんでした。後に「不易流行」と言われる俳句への姿勢は、こうした時期に生まれたのです。
芭蕉が同行の曽良と共に奥州路を訪ねて、土地の俳諧人宅で歌仙を巻くこともありましたが、主たる目的は、古歌の中に遺る歌枕の場所を訪ねることでした。それが昔のままに姿を遺していることは稀で、殆どが荒廃して姿を止めていませんでした。時間経過の中で、姿を変えていくものと変わらないもがあることに着目し、芭蕉は「変わるもの」の姿を見定めると同時に、「変わらないもの」、「変えてはならないもの」をも見抜かなければならないことに気付いたのです。「俳諧の世界も同じである」と。不易(変わらない本質的なもの)と流行(変わるもの、変えなくてはならないもの)の合一の中に、新たな空間が広がり、豊かな感情が生まれる。これが蕉門の俳諧であるとしたのです。こうした考えは、さらに「新しみ」、「軽み」を追求して止まるところを知らず、新しい門下人が次々と登場するのと同時に、古い友は去り、やがては孤高の道を辿ることになります。
芭蕉には元禄二年の暮、上方で俳諧を講じている時期に、もう一つ衝撃的な出来事が生じます。それは19歳まで伊賀上野の藤堂新七郎に仕えますが、その時期、藤堂新七郎は京の北村季吟に俳句を学んでいます。宗房と称して芭蕉も新七郎(俳号は蝉吟)と一緒に俳句を学んだと思われます。その北村季吟と長男の湖春共ども、幕府に歌学方として召し抱えられることになりました。将軍徳川綱吉に歌書を講義するお役目がついたのです。この登用は俳壇の大きな反響を呼び、俳人の羨望するところとなりました。このことは間違いなく上方の芭蕉にも聞こえてきた筈です。元禄2年暮には「何にこの師走の市に行く烏」と詠み、明けて3年正月には「菰をきて誰人います花の春」と詠んでいます。暮に遺した句は「何で暮の忙しい街に、わざわざ飛び出していくのだ。烏の馬鹿は」というような意味に持たせているのでしょうか。烏は誰のことを指しているのでしょうか。
この句からは、芭蕉の「じっとしていられなかった焦燥感」を連想します。中山義秀の著作「芭蕉庵桃青」で、このことを読んだのですが、出仕することなど、考えていない芭蕉とはいえ、目指す俳諧とは異なる派閥の師匠である季吟が、幕府に登用されたとは衝撃を受けたでしょう。元禄3年元旦の句に、京の俳人たちは「お正月早々に菰かぶりの乞食を登場させるとは、縁起でもない」と、非難を浴びせます。芭蕉は西行法師の「撰集抄」にあるように「菰をきた乞食の聖が、大勢いることを西行はとり上げている。その尊い聖を見抜く眼識のないことを恨み、西行を偲んで、詠んだまでのこと」と反論します。この頃に何度も推敲しながら「「幻住庵記」として遺している日記には、「一度は武士の道を志すも成らず、法師を目指しても成就できず、無能無才、風雅を愉しむだけの人間になった。しかし人の一生とはこうしたものではないのか」と、芭蕉は綴ります。
前述しましたように、古い友を失いつつも、新しい門人に囲まれ、常に「新しみ」に挑戦を続けた芭蕉の生涯50年に、魅かれるものが数多くあります。芭蕉俳諧を樹立させるという強い思いが、何度も同業俳諧師から非難を浴びることになりますが、結果的は不死鳥のごとく芭蕉は甦ります。平成の現代においても日本文学界の中に、厳然としたその位置を占める「俳句界の芭蕉」です。ここまで紆余曲折した道程を
辿って来たかも知れませんが、今なお芭蕉俳句の根底「不易流行」が論ぜられています。「芭蕉は今も生きている」と言えるのではないでしょうか。末尾に、前述の「猿蓑」に遺された「幻住庵記」の締め括りに、「秋には実を稔らせて、食糧として人を助けてくれる椎の木だけれど、先ずはこの暑い夏の一日、日影を作って休ませておくれ」という淡々とした気持ちを詠んだ句を記述して、6月の「気ままにご挨拶」にします。(応援団子A)
「先ずたのむ椎の木もあり夏木立」(芭蕉)
|