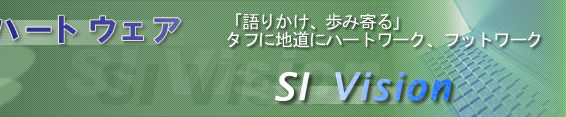六月に入りました。六月といえば「梅雨」の季節です。今年は例年に比べて十日以上も早く、五月のうちに各地区で入梅しました。これは観測史上三番目に早い梅雨入りであるそうです。外回りの多い会社勤務の皆様には、これから暫くの間、鬱陶しい日々を辛抱して、お客様訪問に精を出していただくことになり、農家の皆様には、秋の収穫のことを考えれば、貴重な雨であると拝察致しております。ただ、雨もまた降り過ぎると、育成中の作物を駄目にすることもあり、心配の種が尽きることはありません。自然のことは、なかなか私たち人間の思うようには参りません。
俳句の世界で申し上げますと、この時期の季語に使いますのに「五月晴れ(さつきばれ)」というのがあります。一般的に「五月晴れ」といえばどうでしょうか。私たちには五月五日の端午の節句、鯉のぼりが空を泳ぐ頃の、あの爽やかな好天の青空を想像するのではないでしょうか。ところが、俳句の世界で 「五月晴れ」 といえば、実は「梅雨の晴れ間」のことを言います。以前にも申し上げましたように、俳句歳時記は旧暦に準じて季語を使います。今年のカレンダーを見れば、入梅は六月九日になっておりまして、この日は旧暦でいえば五月三日になり、ここからが梅雨の始まりという訳です。
「五月晴れ」が「梅雨の晴れ間」であるということは、「五月雨(さみだれ)」とか「五月雨(さつきあめ)」といえば、まさしく「梅雨の雨」そのものを言っています。例えば芭蕉の旅日記「奥の細道」の中にも、次の名句が二つ揃っています。
「五月雨を降りのこしてや光堂」(芭蕉)
「五月雨を集めてはやし最上川」(芭蕉)
芭蕉「奥の細道」の旅の目的の一つに、源義経を庇護した藤原三代、平泉の光堂を訪ねることがありました。その金色堂の絢爛たる輝きに流石の五月雨も、光堂には雨を降りのこしている、つまり、降らずに避けているという句です。また山形路を酒田に出るときに渡った最上川での梅雨は、川の流れをはやくし、舟の中で危うさを感じたと記しています。
芭蕉を俳諧の祖と仰いだ、後世の蕪村にも「五月雨」の句があります。その句の中から、ここに二句を挙げます。
「五月雨や大河を前に家二軒」(蕪村)
「五月雨や御豆(みず)の小家の寝覚めがち」(蕪村)
上段の句は、句の「中七」を「大河を前に」と表現したことで、雨で水量が増して、大きく波打つ川の流れの前にある家二軒が、今にも持って行かれそうな危うい情景が目に浮かんできて、梅雨の長雨の恐さまで感じさせるではありませんか。蕪村は絵師でもあります。この句からはそうした一幅の絵まで見えるようで、蕪村の面目躍如たるものがあると思います。 下段の句の「中七」 にあります「御豆の小家(みずのこいえ)」もまた、そこに住いする農夫が、雨が心配で眠ることが出来ない状態を案じる句になっています。ちなみに御豆(みず)は、京都の地区の名前です。
ことほど左様に梅雨の長雨の恐ろしさが、私たちの生活を脅かしていることには、今も昔も変わりはありません。私たちは用意周到の準備をして、出来るだけ被害を少なくすること。これが大切だと思います。六月は長雨の被害に用心しつつ、しかし元気に生活を続けたいと思います。今月もまた「気ままにご挨拶」をお読み下さる皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
(応援団子A)
|