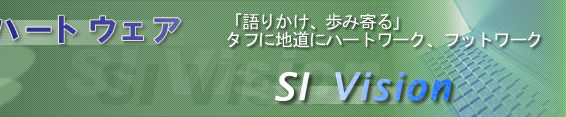「ハートウェア応援団」、しばらくお休みをいただいている間に、四年の歳月が過ぎていきました。「もうこんなに時間が過ぎていたのか」というのが実感です。「もうぼちぼち再開されては」のお誘いを受け、改めて「気ままにご挨拶」から、始めさせていただければと思うに至りました。今、胸を少しドキドキさせながら、キーを叩いております。
8月1日、横浜の地から「富山では、今夜は花火が上がったのだろう」と思っていました。8月1日は富山の空襲被災者に対して鎮魂の花火を打ち上げること、これを戦後ずっと続けてきたことは伺っておりました。数年前にはその花火を拝見したこともあります。今年はもう66回目になると伺いました。67年前まで、世界を敵に回した我が国の戦争の暴挙と辛酸をなめた国民の困難を我々は忘れてはなりません。戦没者の皆さまに謹んで黙祷を捧げます。
お休みをいただいているこの四年間で、応援団子に変わったことがあるとすれば、二年前から俳句の勉強を始めていることです。よく言われるように、俳句は十七音に自分の観察した情景を表現するものだと思っています。ただ、その奥の深さには驚きます。日本語の美しさに誇りを持つと同時に、その言葉を使う難しさを味わっています。何とか俳句になったかと喜ぶよりも、数知れない失敗を続けて恥ずかしく思うことの方がはるかに多いです。
竹西寛子著「詞華断章」に次の言葉があります。著者が作家活動の中で味わっている日本語体験で、「蒼ざめた瞬間」と著者が言われているものです。かの藤原定家の「やまとうたの道、浅きに似て深く、易きに似て難し」という言葉を挙げながら、「蒼ざめた瞬間」を乗り越えるべく、日本語とご自身に挑んでいく心構えを言われております。
『・・・・人のその折々の生きようの「ほど」を、そのまま示す言葉遣いという感
じ方に、振り返ってみると私自身そう早くは至っていない。そう感じるまでには、
人と切り離した言葉の美化があり、自分自身への過信があった。
その、いずれも間違っていることに気づいた幾度かの瞬間を、私は自分の蒼ざめた
瞬間と呼ぶことにしている。この瞬間を経験してから、言葉は誠に頼み難いものに
なり、それに劣らず、自分もいっそう頼み難いものになった。・・・(略)』
竹西さんはこの「蒼ざめた瞬間」の体験を通して、その頼み難い言葉、時としては頼りにならない自分自身の克服に注力された結果、ご自身の進んでいく方向として、「言葉で物事をうつしとるのではなく、言葉で物事を在らせようとする気持ちが強くなり、人の生きようのあらわれとしての古歌に、いよいよ惹かれるになった」とあります。
竹西さんが上述の文中に込められた思いの百分の一も表せませんが、この暑い八月に、上述のような「熱い言葉」に触れることで、恥ずかしながら老躯に鞭を打って読書を続けております。応援団子にも蒼ざめた瞬間と思われる経験はあり、その蒼ざめ方のレベルに違いがあることは、百も千も承知の上ですが、敬愛する竹西さんと同じ体験があることを少しだけ嬉しく思い、これからもその難しい日本語に挑戦する覚悟を決めます。いささか言い訳がましくなりましたが、これをもちましてハートウェア応援団の再開のご挨拶に致します。(A)
|