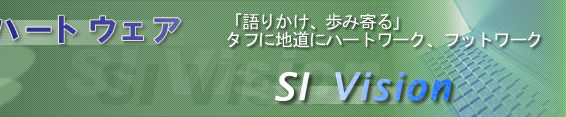この一月からNHKハイビジョンで「日めくり万葉集」が放映されています。この番組は毎週月曜日から金曜日までの朝の6時55分から5分間だけ放送される番組で、現代の各界を代表する著名人が毎日入れ替わり万葉集から好みの一首を選んで、その歌に対する思いを伝えてくれる番組です。万葉集といえば、「気ままにご挨拶」の中でも、大伴家持や山上憶良や高市黒人の歌を何首か選んでご披露したことがあります。(「気ままにご挨拶」のバックナンバー、18年12月「命について」、19年1月「年の始めのご挨拶」、19年12月「いただいたカレンダーから」をお参照下さい。)
このNHK番組も始まってから、すでに50首近くが披露されています。その中には「かもかのおっちゃん」で有名な田辺聖子さんが選んだ歌が二つありますが、その一つを取り上げてみたいと思います。
『来むと言ふも 来ぬときあるを 来じと言ふを
来むとは待たじ 来じと言ふものを』
(大伴坂上郎女 巻四・527)
この歌は来るか来ないかと男を待つ女心を吐露したものです。といっても、この時代の好きな男と女の在り様を説明しなければ歌の意味も通じません。当時、男と女の出会う時間といえば夜であったようです。上流社会では、男が恋文(歌で気持ちを知らせる)を女に送り、それを受け入れた女が部屋に入ることを許す。そして、許された男が女の部屋を訪れるのを常としていました。そんな感覚で歌の意味を読んでください。庶民生活の中ではもっと直裁な方法で、女の部屋に忍び込むというようなことが行われていたのかも知れませんが・・・、それはともかく。
歌の意味は『「今夜は行くよ」と言っても、来ないときがあるくせに、「行かないよ」と言ってよこしたのだから、来ると思って待ってなんかいる訳はないわ・・・。だって、来ないと言うんだから・・・』(筆者の意訳による)ということになります。さて、この女心を受け取った男はどうするでしょうね。こんな男と女の心のすれ違いは、現代でもあるのではないでしょうか。
これはまだ上述の番組で取り上げた人はいませんが(そのうちに出てくるのではないでかと筆者は思っています)、上述の歌が選ばれるとなると、思い出す一首があります。それは作者不詳のものですが次の歌です。
『春雨に 衣(ころも)は甚(いた)く 通らめや
七日(なぬか)し雫(ふ)らば 七夜(ななよ)来じとは』
(作者不詳 巻十・1917)
こちらの方の意味は『貴方は「春雨が降ったから行かれなかった」と言うけれど、あれくらいの雨なら着物がずぶ濡れになるほどではないでしょうに。それなら七夜続けて雨が降れば、七夜も来ないと言うんですか』というようなもので、ちょっと強気な女心を感じ、この歌を受け取った男がオロオロしている姿を想像してしまいます。
今回ここで申し上げたい趣旨は、「万葉歌は我らにとって、もっと身近に親しまれる歌であっても良いのではないか」ということです。これまでの万葉集というと風雅や歴史的背景を強調する余り、どうしても学術的な説明になって、なんだか学校の難しい授業に出ているような気がします。名著といわれる斎藤茂吉の「万葉秀歌」を読んでいても、多くの歌がそんな感じからは免れられません。もっと素朴な人の心情を感じ取るということでよいのではないでしょうか。「日めくり万葉集」で俎上に上がるものは、そうした生活に密着している人々の、心の動きを感じられる歌が多く取り上げられているように思われるのです。
1300年も前に作られた歌、その中から大伴家持が選んだ四千五百余首の中に、現代でも変わらない日本人の心を知るところに万葉歌鑑賞の意味があります。これからも「日めくり万葉集」を楽しみに観ていくことにします。そして、また機会がありましたら万葉歌を登場させましょう。今日は締めくくりに、春を謳歌する志貴皇子の万葉歌をご披露して「気ままにご挨拶」とします。
『石激(いわばし)る 垂水の上の さ蕨(わらび)の
萌え出ずる春に なりにけるかも』
(志貴皇子 巻八・1418)
大きな石の間を流れ落ちる水、そのしぶきを浴びて揺らいでいる緑の蕨。「さあ春が来たぞ!」という喜びの溢れている歌だと思います。毎年、春を迎えるとこの歌を思い出します。あの前途洋々としていた、フレッシュな高校一年生時代を思い出し、元気を出して働こうと思います。さぁ皆さん春ですよ!(A)
|