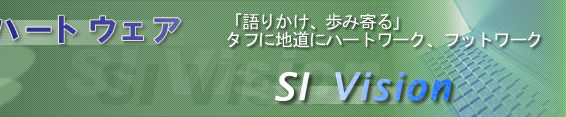もう亡くなられて二十年になりますか。国文学者というよりも、リベラリストという方がピッタリの池田彌三郎さんが、ひょんなことから晩年を魚津の短期大学で教鞭をとられることになり、その時期にNHK富山放送の番組に出演されて、自ら作られた「富山の七不思議」なるものを披露されたことがあるそうです。こういうものです。
身を投げにきた ほたるいか
冬のかみなり 夏の牡蠣
気まぐれ空に あなんたん
寄り廻り波に だけがらす
昔の「今様」の形式にまとめたものだから、七五調の文句なので歌うことも可能であると、池田さんは著作「魚津だより」の中に書かれています。池田さんは、東京の友人への近況報告のつもりで、最初は雑誌「教育の森」に、この「魚津だより」を連載されたようです。後にこれを毎日新聞社から一冊の本「魚津だより」として出版されたと「あとがき」に書かれています。
実は、この本は昭和57年の秋口だったか、当時は一緒の会社で働いていた谷川社長が贈って下さった本です。谷川さんにしてみれば、愛する富山のことを見事に表現した本であり、小生にもそれを伝えたかったのだと思います。今回、読み返してみて、この本が発行されて3ヶ月後に、池田さんが亡くなられていることに気づき、まさに晩年の執筆であることに感慨深いものを覚えました。
前置きはともかく、富山ご当地の方々には上述のことは全てお見通しのことかとも思いますが、本の中で池田さんはそれぞれに詳しい解説をつけておられます。「冬のかみなり」 のところでは「北陸俳句歳時記」 を例に出されて、「鰤起し」あるいは「雪起し」と関連づけられての説明があります。「気まぐれ空」は、土地のことばに「一口荒れ(ひとくちあれ)」というのがあるそうで、「ご飯を一口食べている間に、降ったと思うとまた晴れた」というような変わりやすい空であることの説明も、富山に通うようになった小生には理解できます。「あなんたん」は「穴の谷(あなのたに)」の訛りで、上市町黒川の霊水を言うようです。富山の名水には「イエス」と小生も納得です。
「寄り廻り波」は、富山湾に押し寄せる波が、庄川、神通川、常願寺川などの川口から沖に向かって深い海谷になっているために、反転して次の海岸にぶつかっていく現象のことだそうです。「だけがらす」は「雷鳥」のことだとあります。雷鳥は天然記念物ですから、食べられることはあるはずがないのですが、「これは烏だ」と言い逃れて、昔は食べられたこともあるのかも知れないとあります。どうでしょうか。そんなことがあったのでしょうか。
池田さんは「七不思議などと遊びに走って、大事な富山県について考察の目を狂わせてはならない」ことを自ら戒められていたらしく、このほかに
四十八が瀬 憂き難所
加賀の殿様 かくし路
とか、
風の抑えの 不吹堂(ふかんどう)
盆が二度来る 風の盆
という文句も考えていたことも書かれていて、さらには、越中の地酒や富山湾の魚類、それに雪解けを待ちかねてどっと出てくる山菜類のあることも、頭の中をかけ巡っていたようです。
いずれにしましても富山の春夏秋冬は、日本の季節の「うつろい」を見事に表現している代表であり、それを味わえる素晴らしいところだと思います。今年も年末を迎え、富山では天候不順の日々が続き、「何が素晴らしいもんか」と思われるむきがあるやも知れません。「師走の儀礼」も富山の風習にならえば、皆様にはいつもより忙しい毎日になるでしょう。ですが、池田さんではありませんが、「富山の人間味豊かなお国柄は貴重なものである」ということが、よそ者の目にはしっかりと映っています。
新聞、テレビを見るにつけ、このところ世の中は、あまりにもギスギスとし過ぎているように思います。どうか皆様には「今年もキチンと仕事を仕納めた」と、ご納得のいく富山の年末にしていただきますように、心から念じております。(A)
* 池田彌三郎(1914〜1982)
国文学者、慶應義塾大学文学部部長、洗足学園魚津短期大学教授を歴任する。
慶應義塾大学在職中の1957年から1963年に、NHKテレビ・バラエ
ティ番組「私だけが知っている」にレギュラー出演し、文化人として有名に
なる。1977年紫綬褒章受賞。
|