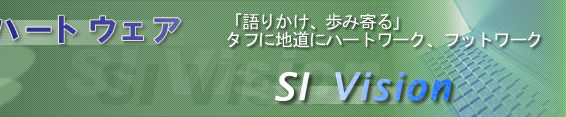遅れ馳せの梅雨が、九州を中心に大雨を降らせ、道路の冠水、土砂崩れと被害が続出しています。もうこれ以上の惨害はご免蒙りたいものです。一方、社会に目を向ければ通常国会が閉会し、いよいよ参議院議員の選挙日が7月29日になりました。
使った事務所費の不透明さ、森林事業に裏金が動いたのではと疑惑をもたれた現職大臣が自殺、年金書類の紛失事件を招いた社会保険庁、失言で防衛大臣が辞任するなど、世間もまた不穏な事件の連続であります。
これ迄だって世の中は、悲惨な事件や多くの不祥事を抱え、すべて解決とは言わないまでも、時間の経過と共にそれなりの落着をみてきました。「世の中なんて、そんなにスッキリした形に収まるもんか」と言いながら過ごしてきたように思います。ところが、何か今までとは違う「空気」の流れを感じています。例えばスポットライトを浴びている本人に報道側から質問をする時、準備された質問の内容、その質問に対する回答、いずれも形式的かつ上滑りになっていませんか。
大宅壮一さんは、嘗てテレビが普及してきた時に「一億総白痴化」という危険信号を表明されました。「なんでもやりまショウ」という番組で、当時は人気があった早慶戦の慶應応援団の真ん中に早稲田の応援旗を持った一人を潜り込ませて、つまみ出されるまでをテレビで撮り続けたというのです。こういうナンセンスなことを喜ぶ番組は、やがて日本人を総白痴化させてしまうと危惧されたのです。
また、政治家とテレビの関係では、「政治家が、テレビに無関心でありすぎるのはどうかと思うし、ある程度の俳優的要素を持ち合わせないと、民主主義時代の指導者にはなれないが、演技過剰な政治家ほどハナもちならないものはない」と言われています。あれからもう50年が経過し、その後、驚くようなパフォーマンスをくり返す政治家もいないではなかったでしょう。それはともかく政治家も報道関係者も、もう一度立ち止まって「報道は如何にあるべきか」を、考え直してもよいのではないでしょうか。
同じ時期に政治家の精神的支柱であられた安岡正篤さんの著作「新撰百朝集」の中に「六然」と題する酔古堂剣掃の名のつく次の言葉があります。(解釈は筆者が安岡さんの解説を参考にして独自にしたものです。)
處自超然(しょじ ちょうぜん)=自分自身を処するには、何事にもとらわれない
ようにしなければならない。
處人藹然(しょにん あいぜん)=人に対してはなごやかに、伸び伸び感じさせる
ようにしなければならない。
有事斬然(ゆうじ ざんぜん) =何か事がある時には、積極的に一歩前に進んで
行動しなければならない。
無事澄然(ぶじ ちょうぜん) =何も事がない場合には、水が澄む如く淡々とし
ていなければならない。
得意澹然(とくい たんぜん) =得意の時には、あっさりと何事もなかったよう
に振舞わなければならない。
失意泰然(しつい たいぜん) =失意の中にある時は、ゆったりと、しかも堂々
としておればよい。
安岡さんは、「我々はとかく處自紛然。處人冷然。有事茫然。無事漫然。得意傲然。失意悄然とでも言うようなことになって、上述のことを達するには余程の修練が必要だ」と解説をされています。これらはもう一度、日本人が身につけるべく心がけなければならない姿勢ではないでしょうか。
今回は、梅雨の最中に少し堅苦しいことを申し上げてしまいました。若い方々には是非とも難しい漢字は辞書を引きながらでも読み、正しく解釈して、先哲の名言を身につけていただきたいと思います。(A)
|