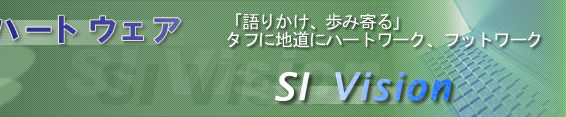|
今年も余すところ十日を切りました。今年の十大ニュースが話題になっている昨今、例年のことながら、世間は何やらざわざわと年末の慌しさが漂っています。皆様には騒々しい表の通りを外れて、静かな裏通りの茶店に上がり、抹茶とお菓子でゆっくりと一刻を過ごす心算になっていただき、この先を読んで下されば幸甚です。今や「スローライフ」が提唱されていて、慌てて生き急ぐのは「ストップ!」と言われます。ここは一つお茶でも啜りながら、芭蕉の俳句、それも年末を詠んだ一句を鑑賞しようではありませんか。(佐藤春夫著「美の世界、愛の世界」から芭蕉の遺した年末の一句を抜粋)
『年暮れぬ 笠着て草鞋(わらじ) はきながら』 芭蕉
著者の佐藤春夫はこの句を「単純に無技巧で、ありのままの境涯をそのまま言い、それでいて趣のふかい不思議な句境である。」と評します。そして「旅の間に年が暮れるというだけのことで、ひとりの旅人の姿がここにはっきりと浮かび出している。しかも芭蕉はその自分の姿をまるで他人事のように見ている」と説明します。だから「年暮れぬ」と表現しても感慨というほどでもなく、何やら世間のことなど忘れて旅をしているという呑気な年の暮れの気分を言っているのだと解釈します。まさに今風のスローライフの心境であるというのでしょうか。
上述の佐藤春夫流を「四十年以上も前から現在のスローライフを予期していた」と考えるのはどうかと思います。これを書いた昭和30年代の日本は、時間がゆっくり流れていたのです。まだまだ呑気なことに抵抗を感じない時代であったと思います。でも観点を「時の流れ」から「心の流れ」に変えて読むと、旅人が笠を着て草鞋の紐を結びながら年末への思いを「あヽ、今年も暮れていくか、次の一年もまた旅の中にあるのだろうが、人生そのものが旅、いつも笠を着て草鞋をはいて歩いているようなものだ」と、旅を人生に置き換えて、来るべき年への決意表明と取ることは出来ないでしょうか。
また「年末といえば、一般的には家族が揃い、お正月を迎える準備をするのが真っ当なところでしょう。それなのに残念ながら遠い旅の空で家族を思い、今日も笠を着て草鞋をはいて、歩いていかねばならぬ。」と、現代風に言えば、ちょっとした哀しきフーテンの寅さんの心境を想起したり、更にはもっと悲壮な一句と考えたりすることも出来るように思うのですが、こんな解釈はあまりにも飛躍しすぎた解釈になるでしょうか。
皆様は果たしてどんな解釈をなさるのでしょうか。俳句について門外漢であり、勉強などしていない者が、 俳聖芭蕉の句にあれこれともの言うのは失礼極まりなく、
ご専門筋からはお叱りを受けるのは必至でしょう。ですが、人の気持ちも千差万別、置かれている立場次第で考えも異なります。多事多難な暗い世相を主体にして考えるのか、WBC(ワールド・クラッシック・ベースボール)の王ジャパンの優勝やイチローの快挙を日本の回復剤に捉えるのか、年末を迎える日本人の気持ちを、あれやこれやと思案してみました。
さはさりながら、悲壮感に顔を伏せて佇んでいても、背筋を伸ばして前を向いて前進しても、どう転びましても年は明けます。来年は亥年、猪突猛進、困難を克服し積極果敢な明るい年にしたいものです。どうぞ皆様におかれましては、ご家族お揃いでご健勝によいお年をお迎え下さいませ。(A)
|