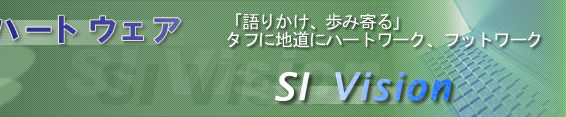|
梅雨時に限った言葉ではないのでしょうが、何故だかこの時期を迎えると「晴耕雨読(せいこううどく)」の四字が浮んできます。これは要職を離れて故郷に帰り、平穏な日々を送り始めた人が「晴れた日には畑を耕し、雨の日には読書三昧に過ごす」状態のことを表現したものです。現代でも仕事に追われ茫々たる日々を過ごしている人は「仕事から解放された暁にはかくありたい」と願う、それこそ退職後の理想の姿なのでしょう。まさに「雨読」の時間もたっぷりとある今日この頃です。カビ臭いと思われるかも知れませんが、江戸時代中期の博学者、西川如見(にしかわじょけん)が著した「町人嚢(ちょうにんぶくろ)」のお話をしたいと思います。
西川如見(1648〜1724)は長崎の人、天文学、地理学を修めた学者ですが、長崎という土地柄、外国から入ってくる知識も頭一杯に詰め込む機会に恵まれていました。専門の「天文学書」や「華夷通商考」の他に、「町人嚢」や「百姓嚢」などの著作を残しました。今回取り上げた「町人嚢」の冒頭には「町人袋をこしらえて世の中のいろんな出来事を取り込んでおき、選び用いようと思っているものの、選ぶ力もなく、さてこれが何の用に役立つのかと、我ながら可笑しくて」とあり、「袋の底も抜けるかもしれないが、笑いぐさにでもなればと思いしたためました」とあります。少し謙遜をし過ぎている序辞ではないかと思いますが、当時、向学心のある町人には絶好の教養書であったと思われます。
その中から一つ選んでお話を進めます。話は殆どが「或る人のいわく・・」で始まるのですが、この話も「或る人の言えるは、」という前置きから始まります。「多くの人が誉める人は善人であり、多くの人が譏(そし)る人は悪人であるという理(ことわり)があるが、衆人の見る目と、天の見るところは逆転することがある。人が見て悪人といわれる人も、天の判断では善人に変わる」と、衆人の判断に疑問符をつけます。例として「物部守屋(もののべのもりや)は、聖徳太子と対立して悪者にされ、聖徳太子といえば誰もが尊敬し誉めるけれども、守屋は深く神道を尊んだ人で悪人ではなく、聖徳太子にもいさぎよくないところがあったと最近の学者が言い出している」とあります。
守屋は日本古来の神道を信じ、聖徳太子は新しく渡来した仏教を信じて、妻の身内の蘇我馬子(そがのうまこ)を味方につけて激しい政争となったのです。軍配は馬子の側に上がりました。ちょうど古代日本立国を海向こうの大国隋に示す時期でしたから、負けた守屋は悪者になり、聖徳太子の憲法十七か条に繋がっていったのだと思います。西川如見は「すべての人は自分に利益のある人を誉め愛し、自分に利益のない人を悪(にく)み、譏るものである」と書き、「悪人と言われる人も委しく尋ねてみれば、そんなに悪業を働いているわけでもない」と言います。守屋の場合は、江戸時代になって学者達が守屋を評価し「必ずしも悪者とはいえない」と言い始めたということです。
永い時を経て、天は別の判断を下したと西川如見は言いたかったのだと思います。「世間の毀誉褒貶に依って、人の善悪は定めがたき理(ことわり)なり。天の思うところを尊び、天の見るところに従っておれば、それは後世に顕れる」とあります。また「逆に表面を如何に取り繕っていても、裏で私心が働いている場合には、必ず化けの皮が剥がれる」とも書いています。人の行動の深層に根ざす核心は昔も今も変わらないでしょう。新聞紙上を賑わしている最近の金の亡者達の格好の悪い話も似たようなものです。「人の振り見て我が振り直せ」と言います。たとえ、少しはカビ臭くて堅苦しい考え方だと思っても、その本質を尋ね、学ぶことは大変実のあることだと思うのですが、如何でしょうか。(A)
|