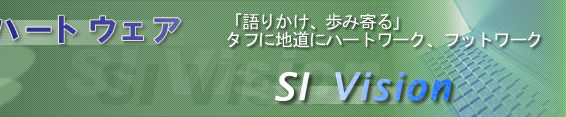|
移動中の車の中で、耳に入ってきたラジオの「身の上相談」話のことです。母親から相談を受けた回答者が「お母さん、もうそれ以上息子さんにお金を渡しちゃ駄目ですよ。息子さんは40歳を過ぎているんでしょ。自分で生活させなくちゃ。お母さんが構わなきゃ自分で何とかし始めますよ」と答えていました。ここまで聞けば私にも相談内容の見当がついてきます。社会性の乏しい生活感のない男が定職にもつかず、母親にお金をせびっているのでしょう。最近よく聞くこの種の話は不愉快を通り越してしまい、「日本人はこんなことをしていていいんだろうか」と不安がつのります。
先日、読売新聞社は「若者の生活と仕事に関する調査」をインターネットによってアンケートし、その集計結果を朝刊のトップ記事にしました。そして、二日後の日曜日に分析の詳細を特集しました。学校に行かず仕事もせず、職業訓練も受けない、いわゆる「ニート」と呼ばれる若者や、定職につかず長くアルバイトを続ける「フリーター」は、在学中に部活やサークル活動もせず、友人も少なく外出もしなかった若者に多く、「一度は仕事についたが働く気力がなくなった」、「自由で気楽にしていたい」、「やりたい仕事が見つからない」という社会不参加型の印象を周囲の人に与えているようです。
「こうした若者にはどのような助けが必要だと思いますか」という問いには、「適性に合う仕事についての相談」、「就きたい仕事の情報提供」が必要だと回答した人が多いのですが、これは周囲の人たちが、困った若者を心配して「相談にのってやってくれ」「情報を提供してやってくれ」と叫んでいるようにも聞こえます。こうした若者の出現は、日本が豊かな生活を獲得してきた裏側で、無防備に育ててしまった腫瘍のように思えてなりません。両親など援助する人がいる間はまだ助かるものの、その人たちが老いを迎えて助けられなくなったとき、どうなっていくのかを考えると恐ろしくなります。
記事の中には「育て上げネット」というNPO法人に入会したことが転機となって前に踏み出した若者の例も記載されていますが、仕事というのは、思い通りにならない苦しさを我慢し、辛抱の上に作り上げるものです。「世の中に適性に合った仕事を探す」とか、「やりたいことを仕事にする」という甘い考え方を捨て、社会に一歩を踏み出すことが大切ではないかと思います。確かに教える側にも「仕事は待ってくれない、教育している余裕はない」と理由をつけて、人を育てることから逃げていますし、教わる側も苦しいことからはすぐに逃げ出し「悪いのは自分ではない」と、人の所為にする弱さがあります。
今、日本の若者に不足しているもの。第一は社会に自分を立たせる勇気です。第二には読書。第三は友人との真剣な会話だと思います。表面的な人との交際、つまり「あんまり深入りすると面倒なことになる」という横着な姿勢や、新聞や雑誌の見出しだけで情報を掴んだ気になっている薄っぺらな独断で平素の生活を送っていれば、そこからは何も生まれてきません。まことしやかに流れる噂話のような情報だけに左右されないように、自分の行動を見つめ直し、人の意見に耳を澄まし、何が本物かを見分ける。こういう生活習慣を身につけるために、良い本を読み、充実した交際をすることです。(A)
(注)読売新聞社が実施したアンケート調査は、若者本人からの聞き取りではなく、
本人について詳しく知っている親族、友人が回答したものです。5月26日(金)
の朝刊に掲載され、5月28日(日)に、紙面二頁に亘って特集されたものです。
|