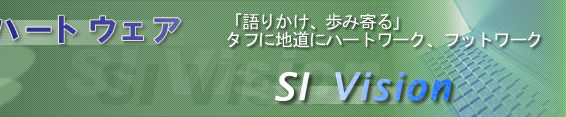|
桜の花の散った、ちょうど今頃の季節を、兼好法師は徒然草の中で上述のように表現しています。この部分は本文第十九段にあり、清少納言の枕草子を思い浮かべながら、この季節を叙述したものと解説されております。兼好法師はこの文章の後を次のように続けています。
『若葉の梢涼しげに茂りゆく程こそ、世のあはれも、人の恋しさもまされと人の仰せられしこそ、げにさるものなれ。五月、あやめふく頃、早苗とるころ、水鶏のたたくなど、心細からぬか は。・・・(略)』
(意訳)
『若葉の梢のみどりが涼しげに色増す季節には、辺りの情景も何かいとおしく、ますます人恋しくなると、ある方がおっしゃっていましたが本当にそのようです。五月を迎えて、軒に菖蒲を葺くころ、早苗をとるころ、水鶏(くいな)がコツコツと、戸を叩くように鳴くころは、まったく心細い気持ちになってしまうものです。・・・』
現代は世の中が忙しくなっているのか。あるいは忙しそうにしているだけなのか。辺りの風景を表現するにしても、ただ「花が咲いた」とか「花が散った」とか、単に見た目の現象を口にしているだけのことで、「身も蓋もない」ということはないでしょうか。兼好法師ほど恋しげに、切なげに季節を表わさないまでも、風が吹いて散り行く花びらに心を残しながら、「若葉の緑がいつの間にか濃くなり、あれだけ待っていた桜の季節も今年は過ぎていきました。時の経過は全くはやいものですね。」と、いうくらいに思うことができれば少しは心豊かにならないでしょうか。
昔から「春宵一刻値千金」とも言われます。過ぎていく今年の富山の春を、松川べりの桜が緑に移りゆく風景を、融けてゆく立山連峰の雪を、時間をかけてゆっくり観賞してみては如何でしょうか。そしてそんな宵は、親しい人と一献傾けつつ、しみじみと富山の「値千金」を語り合えば、富山には心温まる情景も、心ゆすぶる感動も、次から次へ湧き出てくるのではないでしょうか。(A)
|