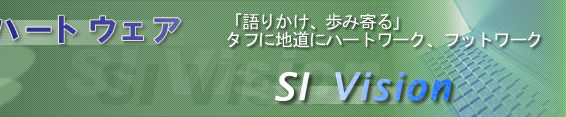|
花の四月を迎えました。前回ご紹介しました富山国際会議場での「花見とシネマの憩いのひととき」も大勢の方々が来場のもとで開催され、「銀座の恋の物語」と「たそがれ清兵衛」が上映されました。会場となった三階の大ホール前のホワイエには、喫茶コーナーが準備されており、来場された方々は、国際会議場メンバーの和やかな応対のもと映画が始まるまで、それぞれお茶とお菓子で会話を楽しんでおられました。
石原裕次郎、浅丘ルリ子主演の「銀座の恋の物語」は、昭和30年代の銀座やその時代に生きた若者の希望を描き出し、「あんな時代があったなぁ」「そう言えば、銀座には電車が走っていたよ」「昔を思い出すなぁ」などの声があちこちで聞かれました。古きよき時代と言われてしまえばそれまでですが、貧しいながらも明日を信じて努力した若者の心意気は、今も生きているものではないでしょうか。
明治維新を間近にした東北の小さな海坂藩に身をおく五十石の貧乏藩士を描いた「たそがれ清兵衛」は、藩内の紛争に巻き込まれ、藩命という名のもとに人を殺めなければならなくなる心の葛藤や、またその相手が剣の名手で、肩や脚に傷を負いながらもやっと勝ち切り、貧しさで中身は売ってしまった武士の魂である刀、竹光を杖にして脚を引きづりながら家にたどりつく場面は山田洋次監督の苦心の作品だと思いました。
この「たそがれ清兵衛」の一コマ。幼い清兵衛の娘が朝食の膳を運びながら暗記した論語を口にしているとき、清兵衛が「これからは女も学問をしなければならない。学問をするということは、『考える力』を養うことになる。『考える力』があれば、人間は生きていける」と娘に言い聞かせます。「考える力があれば人は生きていける」という清兵衛のこのセリフはとても印象的でした。
それにしても昭和を生きてきたオールドボーイ、オールドガールには、青春回復剤となる富山国際会議場の絶好のプレゼントになったのではないでしょうか。花見にはちょっと早かったし、国際会議場の三階ホワイエから大写しに見える富山城公園のお堀が工事中であったのは少々残念ではありましたが、鑑賞のあと、エスカレータを降りていく方々の満足げな表情がそれを物語っていたと思います。次がまた楽しみになりました。(A)
|