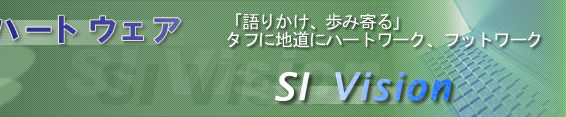『関白様はいまはもう利休に稽古をして貰うようなことはない。でもお茶に関する
かぎり師であり、弟子であることには変わりはなかったし、地方の大名、武将ら
がつぎつぎに参候する場合には、日に数度も催すほどの聚楽第の茶事において、
彼らがこころからうち悦び、国もとへの土産話にしようとするのは、関白様に招
待された光栄にもまして、日本一の御茶頭の御手前を見たこと、どんな名物もの
が飾られ、どんな道具が用いられたかであった。その意味では、秀吉自らが当日
の主人役をつとめようと、まことの主人は疑いもなく利休であった。奉行たちは
もとより、他の誰にならこんなことが許されるだろう。それだけに以前稽古を受
けていたころ、結構とも、お立派、とも賛辞はいっさい述べられず、まあ、まあ、
で片付けられた時の一種劣等感めいた口惜しさに似て、この腹の立つ関係は、そ
れほどの男を顎の先でおい使う自負や満足に交じりあいながら、つねは指先きに
も触れない小さい刺のように、彼の神経の一部にささっていた。』
(十七 から抜粋)
秀吉が強力な武将との均衡を勘案しつつも、利用できる武将は徹底的に利用し、僅かでも弱みを見せる武将は葬り去り、その直感力の鋭さとも緻密さとも言える頭脳で、権力を自らに集中させて絶対的なものとして固めてきたことを、読者に連想させながらこの小説は書き進められていく。綻びの見える者には次から次へと無理難題を押し付けて、その処理方法を見ている秀吉は、お頭として仕えた信長が光秀の謀反で殺されてしまって、譲り受けた格好になった茶頭の利休に対しても同じであった。お茶を立てこれを飲むという生活の一つの句読点にすぎないものを、これを作法化し、さらに茶室や道具を用意することで茶道という一文化にまで高めた利休も、秀吉にとっては絶好の政治手段であり、並みいる武将との非公式な会話、あるいは情の入手方という役割を与えられたのである。秀吉は利休を利用し、利休は利用されることで、総大将である秀吉という権力のすぐ側で自らの位置を獲得した。だが秀吉にとって利休の存在は、利休を家来として支配してはいるものの、上述の文章にもあるように、茶道の上では師匠であることに違いなく、秀吉には「小さい棘」として神経の一部に刺さるところもあったのである。
上述の文章の裏にある背景についてもう少し触れておきたい。北条氏政と氏照の死守する小田原城を豊臣勢が攻めた折には、秀吉の思うように積極的には動かなかった伊達政宗が、北条氏滅亡の後に奥州で起こった小さな土一揆に対して俊敏に動きだした時、秀吉は政宗の謀反を疑って奥州出征を決断したことがあった。小田原攻めでの消極的な行動を政宗が言い訳をして詫びてきた時には、利休が陰になって政宗を助けたことを百も承知の秀吉は、利休に「あの時は一杯喰わされた」と、政宗を助ける側についた利休の態度をしつこく非難し続けた。秀吉の利休に対するいじめ心は、ただわめき散らして、自分に「なんとも申し訳のない次第でございます」と、畳におでこを擦りつけるように詫びる利休を見下ろすことで、刺さっている棘の鬱憤をはらすのである。秀吉の顔には微笑さえ浮かんでいることを著者は書く。結局は政宗の疑いは晴れて、利休にしてみれば何のための平身低頭の詫びであったのかと無念さが溜まることになる。それでも秀吉は利休を必要としたが、「唐御陣」と表現されている朝鮮や明に攻め込む妄想が膨らんで、秀吉の頭の中では堺よりも博多に重点が移り、利休の占める位置は小さく遠くなっていくのである。
著者野上彌生子の方法は、秀吉については弟の大納言秀長、母たる大政所、北政所である禰々たちと交わす対話によって、藤吉郎の頃から関白様に上り詰めて今在ることまでを書き、五十歳を過ぎてますますせっかちになり判断力を狂わせ始めた権力者を書く。利休については妻であるりきと、りきの実兄である弥兵衛、末子の紀三郎を配置して、堺での商人として宗易と呼ばれている利休書く。ついでながら秀吉にも「宗易」と利休のことを呼ばせている。そし
て盟友、織田信長の葬儀を見事に仕切った大徳寺の古渓和尚、さらには茶道仲間の細川忠興や今井宗久を登場させ、中でも利休の一番の愛弟子で、秀吉に茶頭として俸禄していながら二度までも所払いになっている堺の薩摩屋山上宗二の不幸な出来事を、小説の一つの中心に据えた。小田原に来ている師匠の利休を身の危険も顧みず尋ねてきた時、「関白様には挨拶をしていけ」と宗二を促し、挨拶に参上した宗二が、小田原で支援してくれる北条長綱こと幻庵との関係を問い詰められて秀吉にその場で切り捨てられてしまうのである。利休の心の中ではこの事が引き金となって、いよいよ秀吉との抜き差しならぬ終末へと進んでいくが、末子の紀三郎に利休を追い詰めさせる。
紀三郎は小説の中のもう一人の利休である。著者野上彌生子は、表の利休とは別な、普段は心の襞にじっと隠れている自由奔放な本音を吐く利休を、紀三郎に重ねている。世の中のすね者として自堕落な放蕩生活を続ける紀三郎に、上述の山上宗二の惨殺を父親に問う場面がある。紀三郎が「薩摩屋さんでは、宗二さんが死んだことでお父さんを恨んでいるそうですが、何があったのですか。教えてください。私を安心させてください。」と利休に迫るのである。
利休は普段このことを一切口にしなくても、本当は消えてしまいたくなるほど我が身にこたえる出来事であった。「関白様に挨拶に行け」と指示したのは自分であり、宗二が密かに会いに来たことを秀吉に黙っていれば、後からつけ口をされてとっちめられるのは必定と見た。それこそ身が危うくなる。利休は宗二の一本気を人一倍気にかけてはいたが、「関白様のご機嫌次第では許してもらえる」と挨拶のため参上させた。危険な予感を持ちつつも、宗二が上手く挨拶をしてくれることを願った。秀吉は上機嫌で「宗二、殊勝である。茶頭として五百石で召し使う」と声をかけたが、宗二がこれを断わったため関白様のご機嫌が一瞬にして変わり、その場で切り捨ててしまったのである。
紀三郎の疑問に利休は答えられなかった。利休は己の保身のみを考えた自分に滅入るばかりであった。さらに著者野上彌生子は、利休の最終章のためにもう一つの出来事を準備したのである。それは秀吉の側近で「治部」とか「佐吉」と呼ばれる石田三成と利休とのもつれた関係である。三成と利休のバランスは、秀吉の弟である大納言秀長が利休を尊重することで均衡していた。本文では秀吉に「治部は几帳面なたちだから、なんでも一方にかたづけようとする」とか、「彼奴は子供のときからあの通りで、なにをやらせても熱心なら、ごまかしもできない正直者だが、ただ二本の手も一本にして使いたいほうだから、あれだけは始末にわるいよ」と言わせている。「だから秀長は、三成の非妥協的な性格を警戒して、利休を兄の側になくてはならぬ存在としたのだ」と著者は書く。その秀長が長患いの結核で死んで、利休と三成の衝突が始まる。本文では利休の妻りきの兄、弥兵衛の軽口で、三成に「利休が唐御陣は明智攻めのようにはいかぬと言った」と言質を取られ、さらには信長と秀長の葬儀をした大徳寺の三門に利休自らの彫像を飾らせたことで、秀吉に利休の下をくぐらせるのかと難癖をつけられる羽目に陥った。三成のつけ口である。
利休には何度か謝る機会があった。一度は家康を茶室に迎えて馳走をしている。その時にも取り成しを願い出れば良かったのではないか。さらには北政所禰々の側近のゆらという者から妻のりき宛てに手紙を書かせ、返信で利休が詫びてくる機会を与えた。しかしいずれの場合も利休は沈黙した。「ご機嫌取りももう沢山だ」との気持ちが働いていたこともあった。利休は「むざむざと宗二の二の舞にはならないぞ」との用心もあり、さらに何らかのお沙汰が秀吉から直接あることを期待したのだが、秀吉の心だけを読もうとして、三成の心中を読むことを怠った。三成は三成で秀吉の心変わりを警戒し、つねに「秀吉は利休には甘い」と思わせるような言動をした。利休の読み違いは歴然としていて、ゆらに宛てて書いた、りきの返信が秀吉には気に食わず、三成に「あの坊主奴に腹を切らせよ」と命じた。
三成の考えている処罰が遠島ぐらいのことであっても、詰め腹までは考えていないことを承知している秀吉は、戸惑う光成に「詰め腹では手ぬるいか」と追い討ちをかけ、三成が「さすが上様なればこそ」と、あたふたと退出した後に、秀吉を襲ってきたのは利休の存在感の大きさであり、利休の抹殺しか方法はないと思い込むことであった。
著者野上彌生子の「秀吉と利休」には挿入されていない話ながら、何年か前のテレビドラマで、利休が庭一杯に朝顔を咲かせたことが評判になって、秀吉がそれを見に行ったところ、屋敷の庭には朝顔など咲いておらず、秀吉が不機嫌になって部屋に通されたら、床の間の花器だったか、柱にかけられた花器だったかは忘れたが、一輪だけ朝顔が活けられていたというシーンがあり、そのテレビドラマの中では、秀吉がそれをどう思ったのかも憶えていないが、応援団子の気持ちのどこかに引っかかっていた。つい最近になって岡倉天心著「茶の本」に出会い、ここに利休の朝顔の話が記載されており、秀吉が利休のこのもてなしに機嫌を直したとある。天心は一輪の朝顔を残して他は犠牲にする「花御供」の潔さであり、花もその意味をよく知っているのだと書く。豊穣に咲いている花を取り払って一つにすることが美なのか、拵えるよりも自然こそが美ではないのか、応援団子は納得しかねるが、無案内なのでこの話は止める。余談ながら天心は利休の切腹を「茶の本」の末尾で取り上げ、茶室に仲間を呼んで茶を馳走した後、道具は形見として与え、使った茶碗は「二度と決して人に使わせない」と、これを打ち砕いて切腹したと書いている。
著者野上彌生子は、昭和37年(1962年)1月、七十七歳の時に「秀吉と利休」を中央公論に連載し始め翌年8月まで続いた。随所に配置された物語を明確にさせる登場人物の動きや語らせ方は、散在していた資料を読みこなし、すべてを己のものにしてからの見事な執筆であることが応援団子にも分かる。今までもそうだろうし、今後もそうだろうと思うが、「秀吉と利休」が書かれたり、論じたりする場合は、如何なる時も野上彌生子の「秀吉と利休」を避
けて論ずることは出来ないと思う。野上彌生子は昭和65年(1985年)、白寿の年に亡くなった。なお長編小説「森」を執筆中であったという。
これも余談ながら応援団子は、井上靖著「本覚坊遺文」にも目を通してみた。ここでの利休と秀吉の葛藤も興味深い。本覚坊が残した遺文を手にした作者が自分の推理も入れて論ずるという方法で小説は進んでいくが、ここでは利休の死を本覚坊の夢の中で、利休と秀吉を対話させる形で語らせている。「上様が刀を抜いておしまいになったから、宗易は宗易で茶人として刀を抜くしかありません。上様に上様としてお守りにならねばならぬものがあるように、宗易にもまた、茶人として守らなければならぬものがございます。」と利休に言わせるのである。上様が本当の上様に戻られれば利休もまた茶人に戻る。お茶には茶碗と茶入れと茶杓があればよいと言わせることで、茶道に余分なものの生きる道がないことを書く。また、松岡正剛のウエブサイト「千夜千冊」(第九百三十四夜)を訪ねられるのもよい。ここでは野上彌生子の別の一面が見えて、読者にはさらに興味が広がると思う。
昔も今も絶対権力者の行く末は悲しい。秩序の維持のためには権力者は必要であり、人々は権力を持つ者に自らの生活を委ねる。権力者を造るのである。そして必ず自分がこれを造ったと豪語する者が側に出てきて、最初のうちは、それでも奥深く潜んでいるが、時間の経過と共に化け物のように現れ、折角の秩序を壊してしまうのである。こうした実例を探すのにさほどの苦労は要らないと思う。世界の歴史を見ても、現在の国際社会でも、あるいは企業の中にでも容易に事例を見つけることが出来る。権力について人々が考えなければならないのは、秩序を維持する目的の純粋性、無欲でこれに取り組む権力者の選択、人々に迎合することは、求めても、許してもいけないという確固たる意思の強さのことであろう。利休や秀吉に学ぶことは多い。(応援団子A)
|