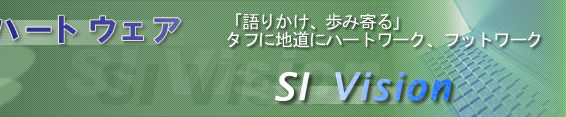今年は作家織田作之助の生誕百年の年。その織田作之助のことを二回に分けて書く。
織田作之助は戦後のどさくさを自由奔放に生きた。結核に犯されている身を削りながら、書き始めれば昼夜を忘れた。作家仲間や雑誌社の人とも酒を飲み、文学を語り、多くの作品を書き遺して昭和22年1月に33歳の若さで逝った。織田作之助は大阪の人であり、大阪を愛した。作品の多くに大阪の街、大阪の店、大阪に住む人が登場する。織田作之助の年譜を見ると、昭和14年に一枝夫人と結婚。翌15年に「夫婦善哉」と「放浪」 を発表している。 そしてこの作品は藤沢恒夫や永井龍男の推挙があったとある。随筆「大阪発見」もこの年の作品である。今回は「夫婦善哉」のことを書く。
小説「夫婦善哉」は、大阪南の繁華街から少し東に外れた横町の長屋が舞台となる。
そこに芋や蓮根、牛蒡や鰯などを揚げて子供たちにも売る天麩羅屋があり、切り盛りしている親父の種吉と女房お辰は、いつも借金取りに追いかけられている。種吉、お辰には蝶子という娘がいて、彼女が「夫婦善哉」の主人公である。小学校を卒業して古着屋へ女中奉公に出るという辺りから話は展開し始める。ご高齢の方はご存じであると思うが、この作品は戦後の昭和30年に森繁久彌、淡島千景主演で映画化され評判になった。 応援団子はまだ高校三年生であったが、 受験勉強を抜け出してこの映画を観た。最近も「夫婦善哉」は、テレビで放映されることがあるのでご覧になった方もいると思う。
とにかく種吉の手筈で勤めた古着屋での女中奉公だったが、種吉が六か月ほどして様子を見に行くと、垢切れて血が滲んでいる手で掃除をしている蝶子がいた。父親はこれ以上勤めさせられぬと古着屋を止めさせた。そして、所望されるままに曽根崎新地のおちょぼ(芸者の下地ッ子)に出した。そこからは一本道ということになるのであろう。芸者への道を、それも父親が躊躇するのを、蝶子自らが押し切って進んでいくのである。一つ間違えば、近所の材木屋の旦那が妾になることを条件に、女中奉公を申し入れてくるような横町界隈の事情がある。蝶子の持っている生来の明るさが、いつも借金取りに追いかけられている父親種吉も、心のどこかでホッとするものを感じていたであろう。
芸者になった蝶子には、お定まりのように男が出来る。梅田新道にある理髪店に化粧品を卸す問屋の跡取り息子、維康柳吉である。女房も子供もいる柳吉は、いわゆる根っからの遊び人で、「美味いものは北にはない、南に限る」と、売れっ子芸者を連れていくような上等の店ではないが、 蝶子を連れ出したし、 帯や着物も買い与えて気を引いた。蝶子の出した手紙と贈った草履が発端となって、柳吉に嫌気がさしていた若い女房は、ついに実家に帰る肚を決めた。中風で寝ている親父も今度ばかりはと「釜の下の灰まで自分のもんやと思たら大間違いや」と勘当を申し渡した。家を飛び出した柳吉は、東京に集金できる当てがあるのを幸い「物は相談やけど、駆け落ちせえへんか」と蝶子に持ちかけた。
二十歳そこそこの蝶子のこと、前後の見境もなく好きな柳吉の話に飛びついた。約束した梅田の駅へ駆けつけてくる蝶子の変に生々しい姿に、ふとそっぽを向いてしまう柳吉の頼りなさに、読者は「大丈夫かな」と不安になるだろう。東京で集金した金で熱海にしけ込んだのは良いが、抱主に無断で飛び出してきた蝶子の心配などには気にも留めず、柳吉は「帰ればまた親父は許してくれるわ」と甘く考えている。二日間ほど遊んだあと、お昼に大きな地震が来た。柱にかじりつきながら我に戻り、「えらい駆け落ちをしてしもた」 という悔いが二人を襲った。 そして大阪に帰った蝶子にとっては、ここからが苦労の始まりとなるのである。遊び人に惚れた女の弱みということか。
読者は「夫婦善哉」を読み進めるうちに、織田作之助の書く維康柳吉という男のことが気になって来ると思う。ひょっと思いついては気の利いたことを言うが、やり始めるとすぐに飽きる。蝶子の心配などは気にも留めず、蝶子がヤトナに出るようになると、蝶子の稼ぐ金を当てにして働きもしない生活力のない男である。おまけに何かと都合のよい理屈をつけては、蝶子が貯めた金を勝手に持ち出しては家には帰って来ない。蝶子もその都度怒り狂うが、結局は許し、同じことを何度も繰り返しながら一緒に暮らしている。始めた剃刀屋を潰し、それならと勤めに出た剃刀屋も長く続かなかった。仔細は後述するが金を貰って始めた関東煮屋も続かず、その後始めた果実の商いも続かなかった。
物語作りの名手織田作之助は、小説「夫婦善哉」の中に、読者が気を揉む場面を随所にちりばめているが、その一つ、中盤を盛り上げている箇所を抜き書きしたい。それは柳吉が親父から勘当を申し渡された後、妹が養子を迎えようとするときのことである。柳吉は蝶子に黙ってふらり梅田新道の実家に戻ったまま、心配している蝶子に連絡もせずにいる。蝶子は父親の種吉に柳吉の様子をこっそり見てきて欲しいと頼んだが、「下手に未練を持たんと別れた方が・・・」と断られ、新世界の八卦見に観て貰うと「男はんの心は北に傾いている」と言われる。十日ほど経った地蔵盆の夜、蝶子が盆踊りの三味線を弾いているところへ柳吉がふらっと顔を出した。織田作之助は次のように書く。
「・・・それでも時々調子に変化を持たせて弾いていると、ふと絵行燈(えあんどん)
の下をひょこひょこと歩いて来る柳吉の顔が見えた。行燈の明りに顔が映えて、眩
しそうに眼をしょぼつかせていた。途端に三味線の糸が切れて撥ねた。直ぐに二階
へつれて上がって積もる話より身を投げかけた。
二時間経って、電車がなくなるよってと帰って行った。短い時間の間にこれだけ
のことを柳吉は話した。この十日間梅田の家へいりびたっていたのは外やない。む
ろん思うところあってのことや。妹が婿養子をとるとあれば、こちらは廃嫡と相場
は決まっているが、それで泣き寝入りしろとは余りの仕打ちやと・・・・(略)」
十日も顔を見なかった柳吉が帰って来たのだから、積もる話より先にと、急いで二階へ連れて上がる蝶子の気持ちは分るし、作者のこの辺りの描写は見事だが、これはまた別の話。短い寝物語で柳吉が喋った話を要約するとこうだ。梅田の家では、「廃嫡というのなら金をくれ」 と迫る柳吉に 「あんな女と一緒に暮らしている者に金をやっても死に金同然や、欲しけりゃ女と別れろ」と言ったきり親父はもうものも言わない。後はもう大芝居を打つだけで、「明日家の者が来よったら、別れまっさときっぱり言うて欲しいんや。ほんまの気持ちで言うんやないねんで」ということだった。「金だけ貰ったら帰って来るから、心配せんでええ。芝居や」と言うが、言われた蝶子は悩んだ。
悩んだ挙句の果てに蝶子は、ヤトナの仕事を斡旋してくれている高津のおきんさんのところに相談に行った。仔細を話したらおきんさんに「蝶子はん、あんた騙されたはる」と言われてしまい、この話にはうっかり乗れないなと思った。梅田から来た使いの者は、手切れ金を持参していた。蝶子はお金を受け取らなかったし、勿論のこと「別れまっさ」とも言わなかった。三日ほど経って、帰って来た柳吉は「お前は阿呆やな。 お前の一言で滅茶苦茶や。ちょっとくらい欲をださんかいな」と不機嫌極まった。結局、親父からは金は取りそこない、妹に無心して三百円を貰って来たという。 これを元手にして二人は相談して、関東煮屋の開店ということになっていくのだが。
もし、蝶子が柳吉の言う通りに手切れ金を受け取ったらどうなっていたのだろうか。
作者の織田作之助もそんな筋書きを少しは考えたに違いない。ただ、ここまで書いてきた柳吉命の蝶子には、かりそめにも「柳吉と別れる」とは言わせられないだろうし、
柳吉の方は、蝶子が手切れ金を受け取っていれば、これ幸いと蝶子の元を逃げ出し、暫くほとぼりの冷めるのを見て、また次の金の出どころを探すような男に仕上げられている。また、作者は柳吉に蝶子の生活力と一本気な行動を、一面冷やかに見つめる目も持たせている。 己のことしか考えない、 しかもそれを利用して生きる男の狡猾さを柳吉に演じさせている。だから物語は、まだまだ波乱万丈の苦難を蝶子に与えていくのである。
ここまでで、もう一つお断りをしておきたいことがある。織田作之助は話を展開させていく中で、読者を納得させる材料としてお金の話を上手く使うことである。例えば、蝶子が梅田新道のおちょぼ(芸者の下地ッ子)に出たとき、父親の種吉には五十円の金が入るのだが、「之は借金払いでみるみる消えたが、あとにも先にも纏まって受け取ったのはそれきりだった」というようにその顛末が表現される。また柳吉が蝶子を連れて駆け落ちしたときのことも、東京にはざっと勘定しても四、五百円の集金があることを書き、この中から拝み倒して三百円ほどを手にして、蝶子と熱海にしけ込んで、あの大地震になるのであるが、あれはまさに大正十二年九月一日の関東大震災のことである。
さらにもう一つ。蝶子がヤトナを始め、二年かけてやっと貯めた三百円の顛末を書くときにも、作者は蝶子が十七歳で芸者に出たときの経緯を挿む。父親の工面で抱主から前借をしているお金を、「あれはもう全部払うてくれたんか」と蝶子に訊かせ、「さいな、もう安心しーや、この通りや」と種吉に証文を出させる。読者も蝶子と一緒になってホッと胸を撫でることになる。もっとも蝶子の貯めた三百円は、柳吉が芸者遊びで百円使って二百円に減ったという話に変化させ、減った百円を蝶子は季節の変わり目ごとに衣裳を質屋に出し入れしてやりくりし、最初の商売である剃刀屋開店の資金に充てる算段話になるのである。お金の出し入れを明確にさせることで、読者には説得性のある物語となる。
第一回目はここで筆を止める。
(応援団子A)
|