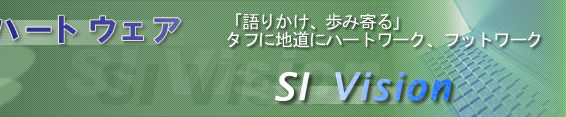藤沢周平作品といえば、映画では、昨年国際会議場でも上映した「たそがれ清兵衛」が話題になり、テレビでは「蝉しぐれ」が評判になった。「隠し剣 鬼の爪」というのもテレビの再放送で観た。映像化された藤沢作品は、観る者の心に何か印象を刻み付けているのではないか。
「たそがれ清兵衛」は、日本アカデミー賞を総取りする勢いであったと思うし、「蝉しぐれ」はアジア・テレビ放送賞を受賞したと思う。もう四、五年前のことで正確な記憶ではないが、いずれにしても藤沢周平が亡くなってからの製作であった。
藤沢周平が亡くなって既に十年が経過した。しかし、書物としての藤沢作品の評判は落ちない。落ちないどころか、評判は日増しに上がってきたように思う。特に世の上級管理職の人達に。これはどういうことなのだろうか。藤沢作品の物語性や登場人物が、現代社会にも通ずる価値観を持ち、読者は主人公の考えに共感し、あたかも自分自身がその中にいるような、そんな感覚で作品に没入しているのではないか。今回は、藤沢周平が二十年も前に書いた「三屋清左衛門残日録」を読み、その魅力の在り様に迫ってみたい。
「三屋清左衛門残日録」は、清左衛門が隠居するに至った事情説明をするところから静かに始まる。跡継ぎの又四郎、里江夫婦にも長男が誕生して三屋家に心配はない。清左衛門は妻を三年前に病気で亡くしており、用人として仕えてきた先代藩主も亡くなった。新しい藩主、新用人への引継ぎも無事に終えたし、これを機に江戸詰めを辞して、郷里に帰って隠居したいとの願いを申し出たところ、新藩主からは「屋敷はそのまま使用しても良い。隠居部屋が欲しければ申し出よ」という破格の厚遇に預かった。
郷里には元服前から同じ中根道場に通って修業した佐伯熊太がいる。今では町奉行として活躍しているが、新しい隠居部屋も落ち着き、又四郎の采配で庭も出来上がったところに、その佐伯熊太が訪ねてきた。「隠居はいいな。自分もまもなく。」と言う熊太に「慌てて隠居などになることはない」と諌める。清左衛門は自分が隠居に収まってみて、意外にも襲ってくる寂しさに狼狽しているからである。熊太の用件は、隠居でなければ出来ないような事件の処理の依頼であった。
爾後、 佐伯熊太の持ち込んでくる事件の解決に注力することになる。 隠居の空虚感を埋めるには絶好の仕事でもあった。「残日録」はそうした隠居ゆえに調べ易い藩内の不祥事や清左衛門自身が気になっている現役時代の残問題を解決していく十五の話から出来ており、その一つひとつはその章の中で完結していくが、全体を通しては、藩内で勢力を競う遠藤派、朝田派という元家老と現家老の派閥闘争が読者の興味を誘う。「 残日録とは印象が悪いのでは 」という嫁の里江に「日残リテ昏ルルニ未ダ遠シ・・」から思いついたと話す。
応援団子は「流石に藤沢作品!」と思うところを紹介できれば本望である。果たしてそんなに上手くいくかどうか。本稿をご覧いただくしかないが、ここでは本書の第二話にある「高札場」を俎上に上げて論じてみる。三十五石をもらう池田家の四男、与之助が家禄百二十石の安富家に養子にいって安富源太夫になり、切腹するまでの話を、藤沢周平が安富源太夫の生き方を通して、言いたかったことを見つけ、それを調べた清左衛門の目を通して語りたかったものを考察してみたい。
お城の正門前にある高札の場で安富源太夫が切腹した。場所が場所だけに町奉行の佐伯熊太にすれば、藩主家に対する意趣があっての切腹ならば大変なことになる。周囲の情報から「どうやらそんな話ではない」ことは掴めたが、真相はどういうことだったのかを一応は調査をしておきたいということで、三屋清左衛門の登場となる。清左衛門は中根道場で修業していた時に、短い期間ではあったが源太夫と一緒であったことを思い出し、道場に出かけて中根弥三郎から安富源太夫が孤立しがちな人間であったことを聞く。
安富家では、家禄の低いところから迎えた養子ということもあって、源太夫には辛く当たった。源太夫がまだ池田与之助であった時に、友世という好きな女子がいたが、若くして死んでいた。「友世を不幸したのは自分のせいだ」と言って切腹したという噂の事実を調べるのが清左衛門の役目であった。上述の中根道場主の話のほかに、源太夫の当時の仲間から聞き出した話で、友世のことや源太夫と友世の関係が次第に明確になってきた。かくして清左衛門はだんだんと真相に近づいていくのである。
清左衛門の調べでは、源太夫はこれまで安富家での冷遇に耐えてきたが、若いときの養子縁組話に血迷い、友世を捨てた申し訳なさがある。清左衛門は言う「若い頃はさほどに気にもかけなかったことが、老境に入ると身も世もないほどに心を責めてくることがある。源太夫の胸の中にも友世に対する悔悟の念がふくれあがり切腹に至った」と。「見事な調べである。これが真相であろう」と佐伯も納得し、安富家に対するこれ以上の調べを打ち切る。大目付にもそのことが報告されて一件落着にはなった。
だが真相は別のところにあった。清左衛門は調べの中で、昔の友世の友達、年江という者のいることを聞いていたが話を聞けていなかったので、「画竜点睛を欠く」を埋めるくらいの気持ちで、年江からその後の友世のことを聞いて見ることにした。その年江の話は意外なものだった。「友世は不幸ではなかった。夫になった人は優しい人で、風邪をこじらせて急死したけれど友世はずっと幸せであった」と。この年江の話から、病弱で不幸な女と思いこんでいた友世が、実はそうではなかったという衝撃を辛うじて受け止めるのである。
藤沢周平はこのクライマックスのところを、『日は相変わらず暑かったが、遠くの空にうかんでいるのは秋の雲だった。――何か、ひどい思いこみをしたようだ。と清左衛門は思った。』と、年江の屋敷から帰っていく場面を淡々と書く。探索の自信がみるみる消えていくのを感じながらも、源太夫もまた誤った思い込みから命をちぢめた皮肉を思い、当分はこのことを誰にも言うまいと、清左衛門が決心することを書く。源太夫の哀れさを思えば、「そんな生涯しか過ごせなかった源太夫のことを人になんか言えるか」ということであろう。
読者は、三屋清左衛門の十五個の隠居生活話から、若い時代の苦い思い出、隠居をするということ、家の中の自分の身の置き所、肉体の衰え、とはいえまだまだ若い者に負けていられるかと湧きあがって来る気概、淡い恋心までも読むことになる。三屋清左衛門の置かれている位置は、現代風に言えば、企業管理職の定年退職後の姿を想像させる。三屋清左衛門が毎日過ごしている姿は、そのまま、読者の今に当てはまるか、でなければやがて迎える定年退職後の自分と思いながら読んでいるか、なのである。
藤沢周平は、若い頃に結核を患っている。手術もしたという。「生きる」ということに対する思いは健常者のそれとは違っていただろう。また不幸にして最愛の妻を病気で亡くしている。戦争も経験し友を亡くしている。「生きる」ということの厳しさを、常に横においての生活であったことが分る。応援団子は恥ずかしながら息女の書かれた「藤沢周平」はまだ読んでいない。でも、これを読めば藤沢周平がもっと好きになるだろう。今年は藤沢周平生誕八十周年の企画もあるという。(応援団子A)
※「三屋清左衛門残日録」
藤沢周平著(文春文庫 1992年9月10日 第1冊)
|