
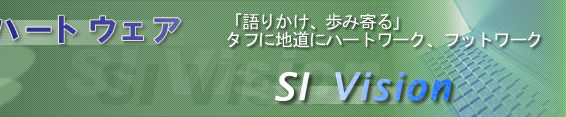
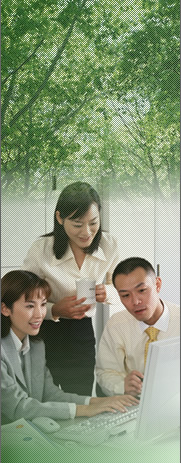 |
第9回◆2005年2月◆ |
|||
| 「全くやる気を感じさせない人。」「何のために転職をくり返すのかわからない人。」と面接をさせていただくことが多くあります。 折角、応募してくれたのだとの思いで、お会いするのですが通じないようです。 「13年前に某建材メーカーでは、入社式に両親も出席してもらう。」(両親から仕事をやめたらと言わせないため) こんな時代に人材の確保が非常に難しいと、七転八倒しております。 昨年末に「経営者、15歳に 仕事を教える」 「人は20代から60代までの40年間、貴重な時間の大半を仕事の場で使います。仕事の場を楽しくすることは、人生を豊かにすることにつながります。」 北城さんの、この本に励まされ”人材確保”出来るまで諦めずにやると奮い立っております。 「第一章」◎仕事とはどういうことなのか」からの抜粋 ※自分のつくったものが社会の役に立っているとわかったときに、「仕事の喜び」を実感できるのです。 ※つくるだけのアマチュアと、止まったときのことも考えるプロ。 ※若いながらも教える立場になれたということも貴重な体験でした。 ※わからなくても、その後の対応さえしっかりしていれば、お客様は不満をもちません。「わからない」といえる勇気をもつことが重要なのです。 ※自分は歳も若かったので、まずは仲間として認めてもらおうと、毎朝お茶くみをしました。 ※お客様にとっては製品が新しいかどうかは二の次。そんなことより、それが自分たちにとってどう役に立つのか、どんなことをしてくれるのか、という話が聞きたいのです。 ※そんなことはいわなくていい、アメリカ人にも英語の下手なやつはいっぱいいる。 ※彼らは、「わからない」といいさえすればきちんと教えてくれますが、何もいわないとわかっているものとして議論を進めます。そうなると、あとで困るのはこちら。なので、必死に質問して、議論についていこうとしました。 ※おたくとは付き合う気がないから、名刺はいらないよといわれた。 ※最初は辛くて退屈でも、半年間辛抱し続けられれば上手になり、自分の成長がみえて勉強がおもしろくなる。
讀賣新聞2005年(平成17年)1月30日(日曜日) 13ページ 本 よみうり堂 著者来店 「恪勤」の合間に書いた より 北城恪太郎さんの恪は恪勤 北日本新聞2005年(平成17年)2月4日(金曜日) 6ページ
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||