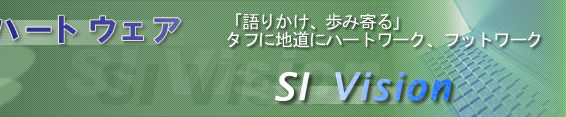| �@�@�NJ��ɂƂ��Ă͓�\�N�߂����Ԃ��o�ċA���Ă����̋��̉z��ł��������A���܂������o�_���f�ʂ肵�Ă���ɖk��A�����̋��{(���Ƃ���)���̋���i�����������ł������炵���j�ɏZ�݂����Ƃ����B�V�C�����悯��Α�ɏo�������H�̕�炵�͕s�ρB�ڂ�ڂ�̑m�߂��܂Ƃ��Ďs���ɎN�����̎p�͈ٗl�ł����Ă��A�NJ��͂��łɂ킪�g��V�^�ɔC���Ă��܂��Ă���A�s�_�����̔@�����X�Ƃ��Ă����Ǝv����B
�@�@���Z�܂������Ă������̉�����������o�āA���l�ɕ߂܂�A�y���߂ɂ��ꂩ�����b���`����Ă���B���߂��悤�Ƃ��Ă���NJ����A���z���a�������ĉƂɘA��ċA�����B���a�́u�ǂ����Ă����܂܂ɖ��߂��Ă����̂��v�Ƃ����₢�ɁA�u�݂�Ȃ������v���Ă��͂��߂����Ƃ�����A����ł����̂ł��v�Ƃ����悤�ȕԓ���NJ��͂����炵���B�����āA�K�����ǖ{�ł����Ă����̂��낤���A�NJ��͏��z�Ƃ̎q���B�Ɏ��������A�܂��ꏏ�ɗV�юn�߂��ƁB���̕ӂ�̗l�q�𐅏�{�i����ג��u�NJ��v�j�ɂ�
�u���̗NJ��ɁA���a���͂����ꂽ�낤���A�悭�l�������Ă݂�ƁA�����̂ӂ����ɑ����Ƃ��Ƃ炳�ꂽ�̂ł���B��H���Q�̒j���A�����L�A�����̋��U�����ō��̐������ƌ��O�ɐ����Ă݂����邬�̂Ȃ�����������B���a�łȂ��Ă��A�т����肷��̂����R�ŁA�NJ��̂����҂łȂ�������z���ł���̂ł���B�v
�Ə�����Ă���B
�@�~�ʎ�����ɂ����l�ɊԈႦ���Ē͂܂������Ƃ�����A��q�Ɠ����悤�Ȗڂɉ�������Ƃ͑O�X��ɂ��������B�u�������]�e(���ɏ]���Ă��炭����̒��ɐg���䂾�˂�)�v�Ƃ�������s���ɔC���ĉ��̂킾���܂���Ȃ��C�s�ʂ͐�ł���A����R�̌܍����ɏZ�ނ悤�ɂȂ��Ă���̗NJ��́A����ɓ������𑝂����悤�Ɏv����B���X�Y�X(�Ƃ��Ƃ�������)�Ƃ��ĉ��₩�Ȃ����ɂ���邬�Ȃ��A�l�ɂ͎����������Đڂ��A�NJ��T�̓��B�_�ɋ߂Â��������Ǝv���B�Ƃ͂����A�ǓƂȓƋ��̎₵���Ƃӂ��ƌ����Ȃ��S�̐Ǝコ��g��ɒ��߂Ă���A��͍����A�Â��ɍ��T��g�݁A�Ǐ��ɂӂ���A���������p��z������ɂ��A�ӂ�ɂ͉����J���̕Y���C�z�ɖ����Ă����̂ł͂Ȃ����B����ȗNJ��̕�炵�����������̎������Ă݂悤�B
�@�@
�@�@�@�@�@�����s�ɏo�Ł@��H���Đ��܂�����
�@�@�@�@�@�������ĔX�̏d�����o��
�@�@�@�@�@�ߒP(�ЂƂ�)�ɂ��đ��̔Z����m��@
�@�@�@�@�@���F�@�����ɂ����肵
�@�@�@�@�@�V�m�@���������Ə�(�܂�)�Ȃ�@
�@�@�@�@�@�s���čs�y�̒n�ɓ����
�@�@�@�@�@�����@�ߕ������x
�i�Ӗ�j�u��������ɏo�Ă��������ƍs��̈���ł������B�����Ă��܂������ɂ͂����Ă��铪�ɑ܂��d�������邵�A�ЂƂ��̈߂ɂ͑��̊������`����Ă���B�̗̂F�͉����ɂ���̂����Ȃ����A�V�����m�l�ɂ��������Ƃ͏��Ȃ��B���ē�����Ă������ɗ��Ă݂�ƁA�����ɐ����t���鋭�����͋����Ă���悤�ɕ������Ĕ߂����B�v
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�w�I���H�������
�@�@�@�@�@�A�藈�����ĖH��������
�@�@�@�@�@�F�ɂ͗t��тԂ�̎Ă���(��)����
�@�@�@�@�@�Â��Ɋ��R����ǂ�
�@�@�@�@�@�������J�𐁂�
�@�@�@�@�@�D�X(������)�Ƃ��Ċ���(�ڂ���)���r(����)��
�@�@�@�@�@���ɑo�r��L���ĉ炵
�@�@�@�@�@�������v�����������^���x
�i�Ӗ�j�u����������A���H���I���A�A���Ă��Ă����̌Âт��˂�߂�B�F�ɗt�̂����Ă����Ă����āA���R����ǂݎn�߂�B�����ׂ͍��J���^��ł��Ĕj����ɐ���������B�\�킸������L���ĐQ�]�肵�Ă₷�炬�������Ă��邪�A���������n�����g�̏�ł����Ă��A���̕s�����Ȃ��^��Ȃǂ���Ȃ��B�v
�@�@�@�@�w�S���@������������@�@
�@�@�@�@�@�V��]�߂ǂ��[������
�@�@�@�@�@��O�킸���ɝ��N(�ׂ���)�����
�@�@�@�@�@�����@���̑O�ɑ͂�
�@�@�@�@�@�V�Ɏ����ĈȂėL�ƂȂ�
�@�@�@�@�@�V�ɏ悶�ĉi���҂炸
�@�@�@�@�@�ꂵ�����ȋ����q
�@�@�@�@�@��(��)�ɏ\�Z(�����Ă�)���(�܂�)����
�@�@�i�Ӗ�j�u�S�̐��͖{���ɐ���ł��邩�B�S�̐��܂��Ă������Ɩ]��ł��Ă��A�S�̒[��͂ނ��Ƃ͏o���Ȃ��B�킸���ɂł���O���N����A���ꂪ�h�����Ċ����̖ϔO���邱�ƂɂȂ�B�����Ă���Ɏ������Ă������甲���ꂸ�A���S�̂Ƃ���ɂ͊҂���Ȃ��B�ꂵ�����Ȗ�������}�l��B���̋���ɑ����̈��Ƃɂ܂Ƃ������̂ł���B�v
�@�@�NJ������R�����D�݁A���q��ǂ�Ŏv���ɒ^���Ă������Ƃ́A�����̕��l�̒���̒��Ɍ�����Ƃ���ł��邪�A�|���q�j���u�NJ��̎��Ɠ����T�v�i�呠�o�Łj�ɂ����R���ƗNJ��̏�q�̎��Ƃ��r���Ă���Ƃ��낪���苻���[���B���R���ł́u�䂪�S�͏H�̌��̕��K�ɐ������������Ɏ�����v�ƁA���Ƃ��ƐS�̖{�͉̂~������̖����̔@�����̍l����̂ɑ��āA�NJ��͏�q�̂悤�Ɂu�S�����ނ��Ƃ͂Ȃ��v�ƕ\������B�u�S�݂̍�l�̕\���ł́A�NJ��̂ق������R�����Ă���v�ƁA�|���͏����Ă���B�܂������ɏo�Ă���u�\�Z�v�Ƃ́A������ł��邪�A���i�A���݂�����A��邳�A���A�p�m�炸�ȂǁA�\�̈��Ƃ������A���R���ɂ��u���A����炤�҂Ɍ�(��)���A�T�݂ď\�Z��ㅂ�锜��v�Ƃ����̂�����ƋL����Ă���B
�@�@����I���ċA���Ă�����̌܍����̕�炵����\�I�Ȃ��̂Ƃ��đS�Ă̐l���F�߂�̂́A�u�lji���^�v�ł͂Ȃ��낤���B���������Ȃ̂ł���������Ɏʂ��̂͏Ȃ����A�t��A���T���I���Ă��NJ��͐Q�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��낤���B�Ƌ��̎₵�����Ԃ߂�ׂ������T�t�́u���@�ᑠ�v�̏��^��ǂ�ŁA�~�ʎ�������v���o�������Ƃ�Ԃ������̂ł���B
�@�@�w�~�ʎ��ŏC�Ƃ�ς�ŁA�������g�Ƃ��Ă͂���i�K�܂ŏC�s���o���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����Ƃ��A����a���ɐ��肵�Đ��@�ᑠ��ǂ܂��Ă�������Ƃ���A����܂œƊw�Őg�ɂ������Ƃ̑��������������Ă��Ȃ����Ƃ��o��A�a���̌��������čs�r���J�Ԃ��āu���@��v������܂ʼn��x�w��ł������Ƃ��낤���B���������ɂƂ��đc�t�̎u�K���Č���ɁA���ɂ��鏔���@�ɍ����邱�ƂȂ��A�܂��ʐ�_����l���Ȃ��A�ܕS�N���������Ԃ��Ă����B�v���Ɍ�p�̉�炪�c�t�̐����Ƃ���𗝉��ł��Ȃ��̂ł͎d���̂Ȃ��Ƃ��낾�낤�B���A�c�t�̎u�������Đ̂����̂Ԃ��̂́A���͂≓�������͂���Ă���A���̑O�ŗ܂��~�܂�Ȃ��B�E�E�E�x
�@�@�Ƒ����Ă����̂����A�NJ��̐S���́A�c�t�����̎߉ނ��p���ŕ����̖{���ł��鑂���@�𐢂ɒm�炵�߂�Ƃ��������Ȏu��m����A���̏��������p�����Ƃ͂Ȃ����܂����Ă��܂��Ă���A�Ƃ�Ȃ��������ł��錻����v���ɂ��Ă��A�S�ɋ�������v���̐��X�̐����͔Y�܂������̂ł������Ǝv���B�܍����ɂ�����NJ��̏C�s�́A�����ł����f������Ό����Ȃ��S�̐Ǝコ��}�����݁A�ǓƂɑς��邱�Ƃł������̂ł��낤�B�ǎ҂͂��̊����͐�����āA�NJ��Ɏv�������炵�Ă���������Ɗ肤�Ƃ���ł���B
�@�@������̂̓��e�Ƃ͕ʂɗNJ��ɂ͎x���҂�F�l�͏��Ȃ��炸���݂����B���̒��ł����(����)�Ƃ̏f��(���キ����)�A�h�d(�悵����)�e�q�̎x���́A�NJ��ɂƂ��Ă͗L��M�d�Ȃ��̂ł������Ǝv���B�܂���ljh�d(����悵����)�������c�����u�NJ��T�t��b�v�́A�㐢�̐l�ɗNJ��̎�������Ă���B�����ʼnh�d�́u�NJ��t�A�g���͍����������Ă��āA��͕@�̒ʂ�����������ځA���ǂŌ����A�_�l�����l�̂悤�Ȑl�ł���v�ƁA�ő勉�̗_�ߌ��t�ł���B����Ɂu�NJ��t���䂪�Ƃɓ�A�O���h���������ɂ́A�Ɛl�͂��ׂĘa�₩�ɂȂ�A�ƒ��ɘa�C���Y���Ă���B�NJ����A���Ă��A�����̊Ԃ͂��̘a�C�������Ȃ��Ŏc���Ă���B�NJ�����Ƙb������ΉƐl�݂͂�Ȑ��X�����C�����ɂȂ�B�v�ƁA�NJ������͂ɗ^�����̓I�Ȓg�����ɂ��Č���Ă���B
�@�@�NJ��̎v�����̂���፷���A���߂̂����錾�t�́A�u���@�ᑠ�v���\�����Ɏc���F�l�ۖ@(�ڂ������傤�ق�)�́u����v���痈����̂Ǝv����i��F�Ƃ́u���F���v�̗��ł���u�C�s�ɗ�ޕ����ҁv�ƈӖĂ��悢�Ǝv���B
�@�@�u���v�͓y�ւ�Ɂu���v�Ə������A�p�\�R���ł͑��M�ł��Ȃ��̂Łu��F�v�Ƃ���j�B�]�k�Ȃ���A�g��G�Y���u�NJ��v�i�A�[�g�f�C�Y�Ёj�̕\�����̑����ɂ́A�NJ����l�ۖ@����ʂ������ꂪ�g���Ă��āu����g�]�n�O�����������j��d���߃m�S���I�R�V�ڈ��m���ꃒ�z�h�R�X�i���E�E�E�v�ƁA�Љ������g���ď����ꂽ�����́A�������ėD�����ǂ݂₷���B
�@�@���؏��O���u�NJ��v�i�}�����[�j�ɂ́u����ƌ����͏O��������ɐ悸���߂̐S���N�����A�ڈ��̌�����قǂ����Ȃ�B�����悻�\���̌���Ȃ��Ȃ�B�����ɂ͈��ۂ�₤��V����B�����ɂ͒��d�̌��t����A�s�R�̍F�s����B�E�E�E�i���j�v�̑S���ƁA���؎��g�������Ƃ��Ƃ���������������A�u����Ƃ́A��F���O��������Ƃ��A�܂������̐S���āA���̎��A���̐l�ɉ������ڈ��̌��t���{�����Ƃł���B�����悻�\���A���������ɂ��Ȃ��B�����̒��ɂ��A����̎҂ɑ��āA���̓����̓��̈��ۂ��f���Ƃ����悤�ȗ�V������B�܂������ɂ͒��d�Ƃ����āA����̌��N���肤���A�̌��t������B�܂�����҂̂��@�����f���Ƃ����N���҂̗�V������B�E�E�E�i���j�v�Ƒ����Ă������A�u�O�������O���邱�ƁA�Ȃ��Ԏq�̔@���v�ƁA�u���̂���҂͗_�߁A���̂Ȃ��҂͈���ށv�v�����A�������݂̐S��Y��ʂ��Ƃ�����Ă���B
�@�@��F�l�ۖ@�́u��ʐl�ɑ��镧�҂̐ڂ����v����������̂ł���B�u����v�̂ق��ɂ́u�z�{�v�A�u���s�v�A�u�����v�̖@������A�u�z�{�v�Ƃ́A�Â炸�ւ�킸�{�����Ƃ������A�u���s�v�Ƃ́A�g���̍���A�S�Ă̏O���ɑ��Ė��ɗ����Ƃł���A�u�����v�Ƃ͎����̋����O���āA��������ɗ����ƁA�����ڐ��ł��̂����邱�Ƃł���B���A�NJ��̏ꍇ�ōl����ƁA�NJ��ɂƂ��āu����v�����A�O���ɑ���u�z�{�v�ł���A��ljh�d�̂�����ljƂɈ��Ă����u�a�C�v�́A�NJ��̌��O�́u����v�ł��낤�B�܂��A�NJ�����̓r���ŁA�q���B�ƈꏏ�ɂȂ��āu��{�V�сv��u�������ځv�ɋ�����̂́A���͂̑�l�����ɂ͊�s�Ɍ����Ă��A����́u�����v�ł���A�₪�Ďq���B����������ɂ�A�g�ɍ~�肩�����Ă�����A�Ⴆ�A��{�V�тɋ����Ă��閺�B�̉��l���͐g���肳��Ă����ł��낤���A���s�̕a�ɖ���Ȃ�����ł����q�����邾�낤�B���A���̎q�B�Ɠ����ڐ��ŗV�тɋ����邱�Ƃ́A�NJ��ɂƂ��Ă͎q���B�ɏo����A���߂Ă��̂́u�z�{�v�ł������Ɖ����c�q�ɂ͎v���Ă���B
�@�@�NJ��ɂ͐S�̎x���ɂȂ�F�l�������B��X�q�z�m����̊w�F�ɗNJ��͎x����ꂽ�B�]�˂�����NJ��ɉ���߂ɂЂƂ͖K�ꂽ�B�����́u�NJ��̏��v�Ɓu�́v�̗F�l�ł���A�����ɂ͎ʂ�����Ȃ����A�NJ��̎c���������������Ă���B
�@�@�V��̎������}����܂ł̐��N�́A�NJ���炤��S��Ƃ̏o����������B��S��Ƃ̉̂̂��Ƃ�͗NJ�������Ȃ��Ԃ߂��B���̒��O�ɂ͐g�̉��̐��b�����Ă�������B���̒�S��Ƃ̉̂̂��Ƃ�̊�����ʂ��Ă��̍e���I��肽���B
�@�@�i�����c�q�`�j
|