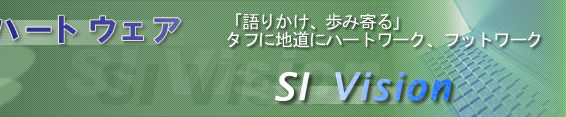『・・(前略)戦勝の狂熱は社会に充満し、浮望空想ほとんどその絶巓(ぜってん)に達したるにおいて、もし講和条約中特に軍人の鮮血を濺(そそ)ぎて略取したりという遼東半島割地の一条を脱漏したらんには、いかに一般国民を失望せしめたるべきぞ。豈(あ)に啻(ただ)に失望せしむるのみならんや、気勢の馴致(じゅんち)するところ、かくのごとき条約は、当時の事情においてほとんどこれを事実に施為(しい)するを許したるや否(いな)やを疑うべきものあり。かく内外の形勢互いに相容れずしてこれを調和することははなはだ難(かた)く、もし強(し)いてこれを調和せんとせば、当時必然、内に発したる激動は、その危害、かえって他日或は外来すべしと推度する事変よりもさらに直大なるを慮(おもんばか)らざるべからず。政府は実にこの内外形勢の難きに処し時局の緩急軽重を較量し、つねにその重くかつ急なるもののために軽くかつ緩(ゆるやか)なるものを後
にし、しかも内難はなるたけこれを緩和し外難はなるたけこれを制限し、まったくこれを制限するわざりしもなおその禍機の発するを一日も遅からしめんことを努めたるは、外交の能事また尽くさざるところありしというべからざるがごとし。(後略)・・』
(第21章 三国干渉[下]結論 からの抜粋)
前回は、明治維新の紛擾を経て成った新生日本の誕生を、敗れた徳川幕府の側にいて苦心惨憺した勝海舟の「三十年後の日本がどうなるかをじっと見てきた」という隠居後の談話を編集した「氷川清話」から日清戦争論を採り上げた。そこでは勝海舟の大局的かつ独創性豊かな日清戦争観を考察したが、日清戦争では清国との間で講和条約締結を終えた直後に、独、仏、露三国から突如として「条約から遼東半島の割譲条件を撤回せよ」との介入があり、実は日本中が大騒動したのである。今回は、その折衝の中心にいた外務大臣陸奥宗光の発言を「蹇蹇録」の中から採り上げた。日本陸海軍の圧倒的な強さで連戦連勝して清国陸海軍を破壊している最中、米国の仲裁を得て駐在公使と連携しつつ紆余曲折を経て、清国との間で講和条約を締結する に至ったが、賠償金を求めたのはともかくも、遼東半島、台湾などの割譲を求めた条文に対し、仏、独、露の三国から前述のように「遼東半島の割地を放棄せよ」との介入であった。歴史上「三国干渉」と言われる事件であり、日本は悩みに悩んだ末、日本はこれを放棄したのであるが、上述は陸奥外務大臣が内外の形勢を沈着に熟慮し、三国の干渉を受け入れつつも、外交上考慮できうる最善の条件下で日清戦争を終結させた背景を釈明した「蹇蹇録」の一部である。
上述の文章の意図するところは、「連戦連勝に日本国民は酔いしれ、戦いに血を流した兵隊の犠牲の上に獲得したという遼東半島の割譲を条約に盛り込まなければ、国内暴動の危険性は計り知れず、諸外国との調整どころの騒ぎではなくなる。内外形勢の軽重緩急を慎重に推し量りながら平和裏に事を収めるのが外交の重要な務めであり、これを全う出来たのではないか。」と、暗に三国からの遼東半島割譲反対という干渉を予想しながら、内外の形勢を調整しつつ「遼東半島については条項から削除するが、南方における台湾などの割譲については不変」という着地すべきところに講和条約を締結させた陸奥外務大臣の心中を吐露したものであろう。この「蹇蹇録」の結論は、ロシアとトルコ戦争におけるサン・ステファノ条約の結果(露土戦争に勝ったロシアがトルコに突きつけた条約に対してイギリス、オーストリア、フランスが反対し、ドイツのビスマルクがロシア寄りの仲介をしたにも拘らず、結果はロシアとイギリスとの内密の取り決めが優先されたこと)を例にあげ、同様に三国の要望を受諾しながらも、「私はこの時期、誰がこれを担当してもこれ以上の良策はなかったと信じている」と、陸奥外務大臣は言い切っており、欧米列強国に伍して帝国主義国家として一等の地位を目指す後進国外務大臣の苦心の結論なのである。
日清戦争当時における日本人の欧米列強に対する劣等感や痩せ我慢をしてでも背伸びする哀しいまでに頑張る姿は、司馬遼太郎著「坂の上の雲」から読み取るのが一番適切だと思う。この小説自体は、伊予愛媛を代表する俳句の創始者正岡子規と、幼馴染で長じて日本海海戦の参謀を勤めた秋山真之とその兄、陸軍大将秋山好古の三人のそれぞれの活躍を通して見た明治日本が、日清戦争を経て結局は日露戦争を迎えざるを得なくなってロシアと戦い、これを破るまでを追跡したものであるが、因みにその司馬の表現の一例を写す。
『・・「明治日本」というのは、考えてみれば漫画として理解したほうが早い。少なくとも、列強はそうみた。ほんの二十余年前まで腰に大小をはさみ、東海道を二本のすねで歩き、世界じゅうのどの国にもない「まげ」と独特の民族衣装を身につけていたこの国民が、いまはまがりなりにも、西洋式の国会をもち、法律をもち、ドイツ式の陸軍とイギリス式の海軍をもっている。「猿まね」と、西洋人はわらった。・・』
如何であろうか。三国干渉が始まった時、独、仏、露の軍事力の脅威に怯えて沈黙した日本人が、講和条約締結後に平穏な日々が続き始めると、先に怯えた憤懣やる方なさを政府にぶつけ、弱腰外交と言い出したことに、陸奥は「人情の自然なるべし」と同情しているが、「奴らに外交の何が判るか」との気持ちでもあったと思う。この陸奥の気持ちにも司馬の表現にも、同じ根っこを持つ日本人の悲壮感の源を見るような気がするのである。
ここで陸奥宗光の生い立ちについて触れる。陸奥宗光の幼名は伊達小次郎、父伊達宗弘は紀州和歌山藩で金融業と地場産業の振興により藩財政を建て直した功労者として勘定奉行を勤めた人である。小次郎も厳父宗弘の下で勉学に勤しんでいたが、九歳の頃、藩内の権力闘争の中で父が失脚、流地され環境は一変した。時あたかも幕藩体制の崩壊がはじまっており、小次郎もまた成長するに従い時の流れに沿い、脱藩、浪人、勤王の志士という道程を辿る。意気に燃えた若武者なら脱藩者だろうと浪人だろうと入所を許した勝海舟の神戸海軍操練所に入れてもらい、坂本龍馬を知ったことで小次郎の生涯はある一つの方向に向かいはじめた。幕府における勝の失脚により海軍操練所閉所後は、亀山社中、土佐藩の海援隊と坂本龍馬と行動を共にし、坂本龍馬を海援隊の社長とするなら陸奥はさしずめ経営企画室長であろう。小次郎はその頃は陸奥陽之助と名乗るようになっていた。伊達という元々東北の一郡の名よりもスケールの大きい国名である陸奥を名乗ることにしたのである。その坂本龍馬が暗殺され、総務部長役を務めていた長岡謙吉ら旧土佐藩の連中としばらく一緒に行動していたが、その後、岩倉具視に外国公使に開国政策を表明することを提案し、伊藤博文らと新政府の外国事務局御用係に任命されるのである。
その後のことをかいつまんでいうと、明治四年までは兵庫県知事や神奈川県知事など貿易港を持ち外国事務が重要な地区の長を務め、伊藤と共に「廃藩置県案」を作成、これを発表したり、和歌山藩の藩政改革に参画し、和歌山藩の執事としてヨーロッパに出向き銃器などの買い付けに従事したりした。思えば坂本龍馬と海援隊時代に考案したと言われている「藩論」を実行に移した時期ではなかったか。ヨーロッパから帰国した明治四年には「廃藩置県」も現実のものとなり、和歌山藩の改革に傾注していた関係上、複雑な心境でもあったと思うが、しばらく財政改革に取り組んだ神奈川県知事も辞任、明治七年には下野し、元老院の幹事等を勤めた。ただこの頃の陸奥宗光は、明治政府の要職は旧薩長藩の人間に限られているという濃厚な藩閥色に猛烈な反意を覚え、明治十年、西郷隆盛が政府に反旗をひるがえした西南戦争の折、旧土佐藩の立志社の連中と政府打倒の陰謀に加担した。これが後に発覚して明治十一年に捕縛され投獄の身となる。五年後に恩赦で出獄した陸奥は、裏切りを許して待ってくれた伊藤博文の厚い友情もあってヨーロッパに遊学、伊藤の勧めでウイーンのシュタイン教授に師事し、イギリスではケンブリッジ大学のワラカー教授からも議会について研究、政治家としての将来に備えていったのである。
明治十九年に帰国して外務省在勤弁理公使に任命され勤務につき、翌々年には駐米公使としてワシントンに赴任した。陸奥宗光は、ここでメキシコとの対等な修好通商条約の調印に成功した。翌二十二年にはアメリカとの改正通商航海条約に調印にこぎつけ帰国、明治二十五年に外務大臣に就任してからは、伊藤博文との好コンビネーションと陸奥自身の識見の高さが諸外国からの評価を受け、翌々二十七年のイギリスとの通商航海条約調印まで、かつて幕府が交わした不平等条約の改正に注力した。陸奥宗光といえば、日清戦争後の講和条約よりも、日本国の地位向上に執念を燃やした「条約改正」を功績にあげる人が多い。いずれにしても明治二十七年から翌二十八年は陸奥宗光にとって、条約改正といい日清戦争の後始末といい、命を賭けた大事業となったのである。事実、陸奥宗光の身体は既に結核に冒されており、三国干渉を受けての会議は静養中の神戸舞子にて開かれたりもした。「蹇蹇録」の擱筆が明治二十八年十二月であり、翌二十九年六月にはハワイで療養に努めたが八月に帰国、翌三十年七月、嘗ての盟友旧土佐藩後藤象二郎の評価があまりにも低いことを憤慨していた陸奥は死の病床の中で「後藤伯」を、筆を手にすることが出来ず口述によって著わした。これが絶筆となり、八月三十日に没した。享年五十四歳。
上述の「後藤伯」で、陸奥は後藤象二郎を評して「彼の不運は放胆不諱の性格に帰するところもあるが、多くは土佐藩の出身であったことによる」と述べる。死を直前にしてもなお、薩長藩閥に対する明治維新の改革への不満は消えなかったのであろう。また後藤象二郎をして何事も成就させなかった政治家といいながら、彼の百敗千挫の中でも前途の計画を夢見て談笑するところを誉め、「当今政治家の気魄、とうてい得ておよぶところあらざるなり」といい、恐らくは海援隊の坂本龍馬はじめ陸奥自らも一員として造り上げた「大政奉還」建白書を徳川慶喜に差し出した日の後藤象二郎の気魄や海援隊員の活躍の日々を、薄れていく意識の中で想起していたに違いない。余談ながら「後藤伯」を読み進めば、坂本龍馬隊長率いる海援隊の面々が若き日、建国に際して発揮した気魄や執念、思いの強さが伝わってくるし、一方では薩長中心に画策された陰謀にも等しき「王政復古」のシナリオの進行など、薩長藩閥政治成立の発芽も推量できる。思えば勝海舟から坂本龍馬へ、坂本龍馬から陸奥宗光へと、内に脈々と流れていた日本建国最終の構図は、国内不戦の明治維新であり、徳川慶喜の政府要職就任であり、議会制民主主義であったと思う。複雑で成立しにくい構想であったと思うが、また別の日本が生まれていたかも知れない。
個人差は勿論あるし一概にはいえないが、この時代の人が持つ気魄や執念、思いの強さは何処から生まれたのだろうか。幼少時からの父母の教えか、教育の方法か、教師の優秀なることか、それとも社会規範が出来ていたのか。
時あたかもアテネ・オリンピック開催を迎える。サッカーのアジア選手権で日本の優勝がある。甲子園の高校野球球児の活躍がある。選手たちのインタビューを聞いていて感ずるのは、勝ち進むには勝ち進む気魄、執念、思いの強さが必要であり、それを選手たちは持っており、名選手には名選手の研ぎ澄まされた感覚、動じない磐石の精神、勝つことへの執念が伝わってくる。負けても言い訳はせず、「失敗の責任は全て己にあり」という気持ちでその場に臨んでいる爽やかさも同時に伝わる。これは時代がどうのこうのという問題ではなく、全般的には現代日本人の日頃の怠惰な精神に問題があるのだろう。陸奥宗光の話が、とんだ横道に逸れてしまった。なお中公バックス「日本の名著
陸奥宗光」には「蹇蹇録」のほかに、宗光が家族に宛てた手紙も掲載されており、宗光の家族への思いも伝わってくる。(応援団A)
|