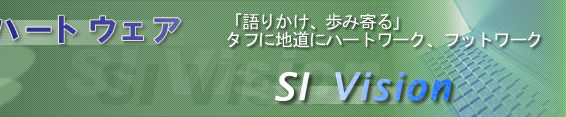『あの方の唄と三味線の音が聞こえてきたとたん、ほかの話し声や物音はいっぺんに消えてしまい、その唄と三味線の音いろだけが、あたしのぜんたいを包んでしまった。ほとんど忘我の状態のなかで、あたしは自分の体の中をなにか風のようなものが吹きぬけるのを感じ、それにつれて少しずつ、全身が透明になってゆくように思った。――蝶になる、あたしは蝶になってしまう。夢とも現実とも、はっきり区別の出来ない気持ちで、あたしはそう呟いたものだ。』
本年は、山本周五郎の生誕百年の年ということで、新聞や雑誌に山本周五郎の話題が掲載されていることが多かった。この12月に入って、石井ふく子がプロデュースし、宮沢リエが主演する「初蕾」という記念ドラマ番組も放映された。山本周五郎の本名は清水三十六(さとむ)と言う。明治36年(1903年)に生まれたので、三十六(さとむ)と名づけられたと伝書にある。山本周五郎という名前は、三十六少年が奉公していた「質屋」の主人の名前を無断拝借していたらしい。作品が認められるようになった後で主人に会い、許しを乞うたと聞いた。「虚空遍歴」は、昭和36年から38年まで雑誌「小説新潮」に連載された長編小説であり、短編小説が得意と言われていた作者が、世間に安直な評判が定着するのに反旗をひるがえした訳でもないのだろうが、後に著した「樅の木は残った」、「ながい坂」と共に、山本周五郎三大長編小説と言われているものの一つである。
物語の主人公「中藤冲也」は、武家の出ながら端唄の名手であり、今流に言えばまさにシンガー・ソング・ライターということになる。上述の文頭にある「あの方の唄と三味線」の「あの方」とは「中藤冲也」のことであり、これを話しているのは、出戻りの松廼屋の実の娘で、そこから座敷に出ている芸者「おけい」のことである。この物語は、上述のような「おけい」の独り言から始まる。座敷に出るようになった或る日、どこかの部屋から聞こえてくる「冲也」の端唄を初めて聞いた「おけい」が、その声と調子に感動した様を表現したのが上述の抜粋なのである。この運命的な出会いが発端となって、「おけい」は、「冲也」の苦悩の渦に巻き込まれていく。実は「冲也」は評判の良い端唄とは別に、何とか浄瑠璃をものにしようと遍歴を続け、周囲には信じてもらえないが、妻ある身の「冲也」と「おけい」は男女関係抜きで起居を共にし、浄瑠璃創りに邁進する物語である。
短編であれ長編であれ、山本周五郎の作品は、読者を押しつぶさんばかりに強烈な重圧感で迫ってくるものが多い。
読者は、物語の主人公が背負う苦境と闘い、一緒になって耐え、逃げ出しそうになる気持ちを振り払って思いとどまり、一緒になってこれに立ち向かう。そして、耐えに耐えた末に身に降りかかる運命を受け入れ、主人公が自らに語りかける心底からの「言葉」に、読者は作者の思いを知るに至り、胸を熱くするのではないか。例えば、短編集の名著「青べか物語」の終末近くに「留めさんと女」という章があり、居酒屋の満座の中で一杯の酒にありつくために、女にバカ呼ばわりをされ、踊らされる薄幸の水夫「留めさん」の悲しき境遇を思い、屈辱感に震えながら、主人公に呟かせる「苦しみつつ、なおはたらけ、安住を求めるな、この世は巡礼である」という、主人公が愛読していたストリンドベリイの「青巻き」の中の一句を掲げるのもその一つであろう。
「虚空遍歴」に話を戻すと、中藤冲也はおけいの想像を絶する献身的な助けを得ながらも、結局、目指した浄瑠璃で思うような作品を残すことが出来なかった。作品が出来ない苦悩、人に理解してもらえない悶えの中で、好きな酒の力を借り、身体を痛めつけて死んでいくのであるが、ここでも山本周五郎は、自ら座右の銘としたブラウニングの言葉「人間の真価は、その人が死んだとき、何を為したかで決まるのではなく、彼が生きていたとき、何を為そうとしたか」を、「冲也の生涯」に埋め込み、文学の世界で困難にぶつかっていく自分自身の決意を表明したのだと「あとがき」に奥野建男は書いている。とはいえ、ここに書かれた「冲也の生涯」は上出来の部類に属すると思う。殆どの人間は、何かが出来たと思った人――実は錯覚の場合が多い――は別として、自分の夢を実現することもなく、大抵は強烈な挫折を仕舞い込んだまま、一生を終えるのではないか。
ところで、今回、応援団子が言いたかったのは中藤冲也にみられるような運命のはかなさのことではない。「おけい」が「忘我の状態の中で身体を吹き抜けていく風」と感じ、「全身が透明になって」、果ては「蝶になる」と、表現した感動についてであった。幸いにもここまで生きてきたお陰で、感動を味わった経験は少なからずあるが、ここで表現されているような感動に出会えた記憶は残念ながらない。僅かに「これに近いか」と思われる、今を去る二十数年前に、富山への出張時に味わった感動――音楽に情景が重なっての感動であったが――を披露したい。
当時は東京、富山間の出張は、羽田空港と小松空港の往復フライトを利用していた。その日もお得意様とのハードなネゴシエーションを終えて、ようやく予定の飛行機に乗り込み、小松空港から羽田までの帰京時間を寛ぐつもりでいた。やがて飛行機は飛び立ち、耳にしたイヤホンから流れてくるマントバーニー・オーケストラ楽団の奏でるメロディーが疲れた神経には心地よかった。おりしも、暮れなずみ次第に藍色を濃くしていく空を背景に、白雪に覆われた立山連峰の夕日を浴びて赤く染まった壮大な美しさが、小さな窓一杯にひろがった。時間にして三十秒にも満たない時間であったと思うが、忘我の境地と言えるような、「おけい」の表現に近い感動であったのではないかと思う。
飛行機の高度が上がるに従い、落日に合わせて、何処までも長く伸びる雲の上部は、茜色を一直線に引いていたが、やがて夜の暗黒に溶け込んでいった。
立山連峰は、その後も春夏秋冬、富山を訪ねる度に、出会うことの楽しみの一つになっているが、残念ながらその姿を見せてもらえない日も多く、ある時には、雲間からその雄大な姿の一部を現したと思った瞬間、あっという間に姿を隠してしまう。夏には、青黒い雄姿が迫ってくるように見え、そのスケールの大きさを感じさせてくれもする。
これからはいよいよ年末、寒風と曇天の冬日々が続く。あの日と同じような感動を追いかけるのは無理としても、いつかはまた違った感動の立山連峰に出会えるのではないかと、富山に来る度に、たとえ雨の日であっても、「あの辺りに立山連峰がある」と確かめて、嘗て味わったあの情景を思いつつ富山の街々を行き来することになる。年末年始、皆様にはお健やかなる日々を。どうぞよいお年をお迎え下さい。(応援団A)
|